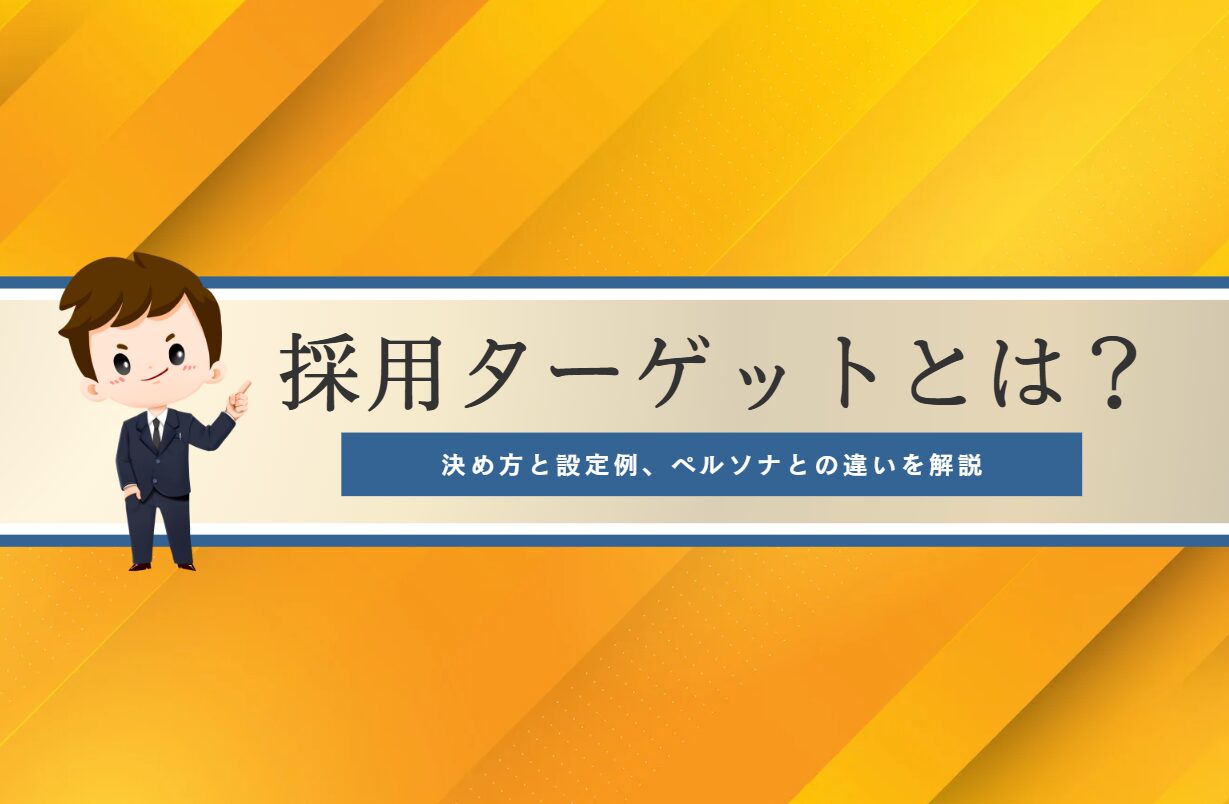
採用ターゲットとは、自社が採用したい人物像を具体的に定義したものです。
採用活動を成功させるには、どのような人材を求めるのかを明確にする採用ターゲットの決め方が重要になります。
この記事では、採用ターゲットの基本的な考え方から、具体的な設定方法のステップ、職種別の設定例、そして似た概念であるペルソナとの違いまでを網羅的に解説します。
目次
そもそも採用ターゲットとは?採用ペルソナとの違いも解説
採用ターゲットとは、採用したい人物の経験、スキル、価値観、志向性といった要素をまとめた人物像のグループを指します。
一方、採用ペルソナは、ターゲットをさらに掘り下げ、年齢、居住地、趣味、休日の過ごし方といったプライベートな情報まで含めて、まるで実在するかのような一人の人物像として詳細に設定するものです。ターゲットが「層」を指すのに対し、ペルソナは「個人」をイメージする点で異なります。採用ペルソナの設定方法は以下記事参考にしてください。
【テンプレート付】欲しい人材を確実に採る為の採用ペルソナ設定方法
採用ターゲットを明確に設定すべき3つの理由
採用活動の成功には、採用ターゲットの明確化が欠かせません。
求める人物像が具体的であればあるほど、採用に関わる全てのプロセスで一貫性のある判断が可能になります。
これにより、選考の精度向上、候補者への効果的なアプローチ、そして入社後のミスマッチ防止といった複数のメリットが生まれるため、自社の採用力を高める上で重要な工程といえます。
採用活動の軸がぶれなくなり選考の精度が上がる
採用ターゲットの明確化は、採用活動における共通の判断基準を設けることにつながります。
求める人物像が具体的に定義されていると、面接官ごとの評価のばらつきが抑えられ、誰が評価しても一貫性のある選考が実現できることがポイントです。
感覚的な判断ではなく、設定した要件に基づいて候補者を評価するため、自社にとって本当に必要な人材を見極める精度が高まります。
結果として、採用のミスマッチが減り、組織全体のパフォーマンス向上にも貢献します。
候補者へ的確にアプローチでき応募が集まりやすくなる
採用ターゲットの明確化により、その人物像がどのような情報を求めているか、普段どの媒体を利用しているかといった行動パターンを予測しやすくなります。
これにより、採用ターゲットの心に響く求人広告のキャッチコピーや、スカウトメールの文面を作成し訴求することが可能です。
また、ターゲット層が多く利用する求人サイトやSNS、イベントなどを選んでアプローチできるため、採用活動の効率が向上します。
的確な情報発信は、求める人材からの応募を増やす上で非常に効果的です。
入社後のミスマッチが減り早期離職を防止できる
採用ターゲットの明確化は、候補者が持つスキルや経験だけでなく、企業の文化や価値観との相性を見極める上でも役立ちます。
自社の社風や働き方に合致する人物像をターゲットとして設定することで、入社後の「思っていたのと違った」というギャップを未然に防ぎます。
候補者も、企業が求める人物像を具体的に理解できるため、自身のキャリアプランと照らし合わせやすくなります。
結果として、入社後の定着率が高まり、早期離職の防止につながるのです。
【4ステップで簡単】採用ターゲットの具体的な決め方
採用ターゲットの設定は、闇雲に進めても効果的な人物像を描くことはできません。
採用活動の成功確率を高めるためには、体系立てられた手順を踏むことが重要です。
ここからは、誰でも実践できる採用ターゲットの具体的な決め方を4つのステップに分けて解説します。
この流れに沿って検討することで、自社に最適な人物像を具体化できるでしょう。
ステップ1:採用の目的と求める役割を定義する
採用ターゲットの設定において、最初のステップは「なぜ採用するのか」という目的を明確にすることです。
欠員補充なのか、新規事業の立ち上げに伴う増員なのか、あるいは組織の若返りを図るためなのか、背景によって求める人物像は大きく異なります。
採用目的を定義した上で、その人材にどのような役割を担ってほしいのか、現場や各部署とのすり合わせを行い具体的なミッションや期待する成果を洗い出します。
この工程が、後のステップで設定するスキルや経験の要件を定める土台となります。
ステップ2:自社の魅力と採用市場の動向を分析する
次に自社の現状を客観的に分析します。
事業内容、企業文化、働き方、給与水準といった要素を洗い出し、候補者にとって何が魅力となるのか(強み)、何が懸念点となるのか(弱み)を把握します。
同時に競合他社の採用動向や、採用市場全体の需給バランスも調査し、現実的に採用可能な人材のレベル感を見極めます。
この内外の環境分析を通じて、理想論ではない、実現可能性の高い採用ターゲットの設定と採用戦略基本設計が可能になります。
ステップ3:必要なスキルや経験を「MUST/WANT」で整理する
採用したい人物に求めるスキルや経験、資格といった要件を具体的にリストアップします。
このとき、全ての項目を同列に扱うのではなく、「MUST(必須条件)」と「WANT(歓迎条件)」の2つに分類することが重要です。
MUSTは、この条件がなければ業務遂行が困難な最低限の要件を指します。
一方、WANTは、必須ではないものの、あればより活躍が期待できる要件です。
このように優先順位をつけることで、採用基準が明確になり、採用ターゲットの範囲を柔軟に調整できるようになります。
ステップ4:現場社員の意見をヒアリングし人物像を具体化する
最後に、採用後に一緒に働くことになる配属先の現場社員にヒアリングを行うことをおすすめします。
実際に現場で活躍している社員に共通する特性や、業務を円滑に進める上でどのような人物が適しているかなど、現場ならではの視点から意見を求めることが失敗を防ぐために重要です。
人事担当者だけでは見えにくいリアルな情報を得ることで、机上の空論ではない、地に足のついた人物像が描けます。
このヒアリングを通じて、採用ターゲットの設定の解像度が一気に高まります。
【職種別】採用ターゲットの設定例を紹介
ここまでの決め方を踏まえ、実際の採用ターゲットの設定例を職種別に紹介します。
理論だけでなく具体的な例を見ることで、自社で採用ターゲットを設定する際のイメージがより明確になるでしょう。
今回は、多くの企業で募集される機会が多い「中途採用の営業職」と「新卒採用のエンジニア職」の2つのケースを取り上げます。
例1:即戦力となる中途採用の営業職
この例では、法人向けSaaSプロダクトの新規顧客開拓を担う営業職を想定します。
MUST要件として「法人営業経験3年以上」「IT業界での実務経験」を設定し、即戦力として自走できる能力を求めます。
WANT要件には「SaaSプロダクトの営業経験」「チームリーダー経験」を置き、将来の幹部候補としてのポテンシャルも視野に入れます。
人物像としては、目標達成意欲が高く、論理的思考力に基づいて顧客の課題を解決できる人材をターゲットとします。
例2:ポテンシャルを重視する新卒採用のエンジニア職
この例では、自社開発Webサービスの開発チームに配属する新卒エンジニアを想定します。
実務経験がないため、ポテンシャルを重視します。
MUST要件は「プログラミングの基礎知識(授業や独学で可)」とし、最低限の素養を確認します。
WANT要件として「個人でのWebサイトやアプリの開発経験」「技術ブログでの情報発信経験」を設定し、学習意欲や主体性を評価します。
人物像としては、新しい技術への知的好奇心が旺盛で、チームメンバーと協力しながら開発を進められる協調性を持つ人材をターゲットとします。
採用ターゲット設定で陥りがちな3つの注意点
採用ターゲット設定は採用活動の根幹をなす重要なプロセスですが、進め方を誤るとかえって採用の妨げになることもあります。
ここでは、ターゲット設定を行う際に特に陥りやすい3つの注意点を解説します。
理想が高すぎる非現実的な人物像にしない
採用ターゲット設定において、現場の要望をすべて盛り込んだ結果、あらゆるスキルや経験を完璧に備えた「スーパーマン」のような人物像を描いてしまうケースがあります。
しかし、そのような人材は採用市場にほとんど存在しないか、存在したとしても多くの企業が求めるため採用競争が激化します。
自社の事業フェーズや魅力で惹きつけられる現実的な範囲で採用ターゲット設定を行うことが重要です。
MUST/WANTで要件に優先順位をつけ、ターゲットの幅を適切に保つ意識が求められます。
応募資格と求める人物要件を混同しない
ターゲット設定の際には「応募資格」と「求める人物要件」を明確に区別して整理する必要があります。
応募資格は経験年数や保有スキル、資格といった客観的に判断できる定量的な基準です。
一方、求める人物要件は協調性や主体性、価値観といった定性的な側面を指します。
これらを混同して求人票に記載すると、候補者に企業の意図が正しく伝わらない可能性があります。
ターゲット設定の段階で両者を分けて定義し、それぞれを適切な方法で伝える工夫が求められます。
一度設定したターゲットに固執しすぎない
採用活動を開始する前に緻密な採用ターゲット設定を行うことは重要ですが、その設定に固執しすぎるのは避けるべきです。
採用活動を進める中で、想定していたターゲットからの応募が全くない、あるいは面接で出会った別の層の候補者に非常に魅力的な人材が多い、といった状況も起こり得ます。
市場の反応や応募者の傾向を見ながら、採用ターゲット設定を柔軟に見直す姿勢も必要です。
当初の計画に縛られず、状況に応じて軌道修正することが採用成功の鍵となります。
設定した採用ターゲットに響くアプローチ方法
採用ターゲット設定が完了したら、次はその採用ターゲットに自社の魅力を効果的に伝え、応募へとつなげるアプローチを考える段階に移ります。
設定した人物像がどのような情報を求め、どのような媒体に触れているかを基に、戦略的な情報発信を行うことが重要です。
ここでは、求人情報の作り方と採用手法の選び方という2つの観点から具体的なアプローチ方法を解説します。
採用ターゲットの興味を引く求人情報の作り方
採用ターゲット設定を行うことで、候補者が仕事選びで何を重視するのか求めるニーズが見えてきます。
例えば、成長意欲の高い若手層をターゲットとするなら、挑戦的な仕事内容や研修制度、キャリアパスの多様性をアピールします。
一方で、安定志向の層がターゲットであれば、福利厚生の充実度やワークライフバランスの取りやすさを強調するといった工夫が考えられます。
ターゲットのインサイトを深く理解し、その心に響く言葉を選んで求人票やスカウトメールを作成することで、訴求力を高め、応募の動機形成を後押しできます。
求人情報には採用ターゲットにお伝えすべきキーワードを資料に書き出し選定しておくと失敗しない求人情報の掲載やポイントを押さえ訴求力が高まりやすいです。
採用ターゲット層に合わせた最適な採用手法の選び方
採用手法は多岐にわたりますが、ターゲット設定に基づいて最適なチャネルを選択することで、採用活動の費用対効果を高められます。
例えば、専門性の高いスキルを持つ人材を探す場合は、専門職向けの求人サイトや技術者コミュニティ、リファラル採用が有効です。
若手のポテンシャル層にアプローチしたいのであれば、就活イベントやダイレクトリクルーティング、SNSを活用した採用広報が考えられます。
ターゲットが日常的に利用するプラットフォームを見極め、そこに集中的にリソースを投下することが成功への近道です。
採用ターゲットに訴求する採用ピッチ資料(動画付きも可能)の作成も面接対策におすすめです。
まとめ
採用活動の成果は、採用ターゲットの設定の精度に大きく左右されます。
自社が本当に求める人材を明確に定義することで、選考の軸がぶれなくなり、候補者へのアプローチも的確になります。
結果として、入社後のミスマッチが減り、組織全体の成長に貢献する人材の獲得が可能です。
本記事で解説した4つのステップや注意点を参考に、自社の採用目的や現状に即した採用ターゲットの設定を行い、採用活動を成功に導いてください。
bサーチでは100種類以上の採用サービスを取り扱っています。
市場に採用ターゲットがどれくらいいるか調査し採用ターゲットを決めることも可能です。
採用戦略策定や競合調査もご支援します。お気軽にお問合せください。
採用ターゲットとは、企業が求める人材像を明確にし、どの部署で活躍できるのか、どんな条件や基準をもとに選定するかを整理するための 基本的な設計ステップ(step) です。新卒・中途ごとにニーズや傾向が異なるため、採用戦略を立てる際には、媒体選定、選考フロー、面接評価のすり合わせまで一貫して考える必要があります。採用ターゲットを明確に決めることで、訴求力の高い募集文や資料作成が可能になり、キャリタスやuc、企業サイト、dl資料などの媒体活用においても効率が大幅に向上します。
一方、似た概念である 採用ペルソナ(ペルソナ設計) は、より詳細な人物像を描く手法で、具体的な年齢・経験・価値観まで踏み込む点が採用ターゲットとの違いです。採用ターゲットが “方向性を決めるための基準” だとすれば、ペルソナは “実際の訴求内容に落とし込む詳細像” といえます。両者を正しく使い分けることで、マッチ度の高い候補者にアプローチでき、競合との差別化にもつながります。
決め方としては、まず社員の活躍傾向を分析し、必要なスキルセットや価値観を項目ごとに整理します。そのうえで、対象層が感じるメリットやnegative要因を把握し、求職者がどの時点で離脱しやすいかまで実践的に検証することが重要です。おすすめの手法として、過去の採用データや面接評価の振り返りを行い、目的に合わせた訴求ポイントを細かく策定すると失敗しにくくなります。
採用ターゲットの明確化は、採用活動全体の成功を左右する重要工程です。記事のまとめとして、ターゲット設定は採用戦略の土台であり、ペルソナとの違いを理解したうえで精度を高めることで、より効果的な人材獲得が可能になります。

