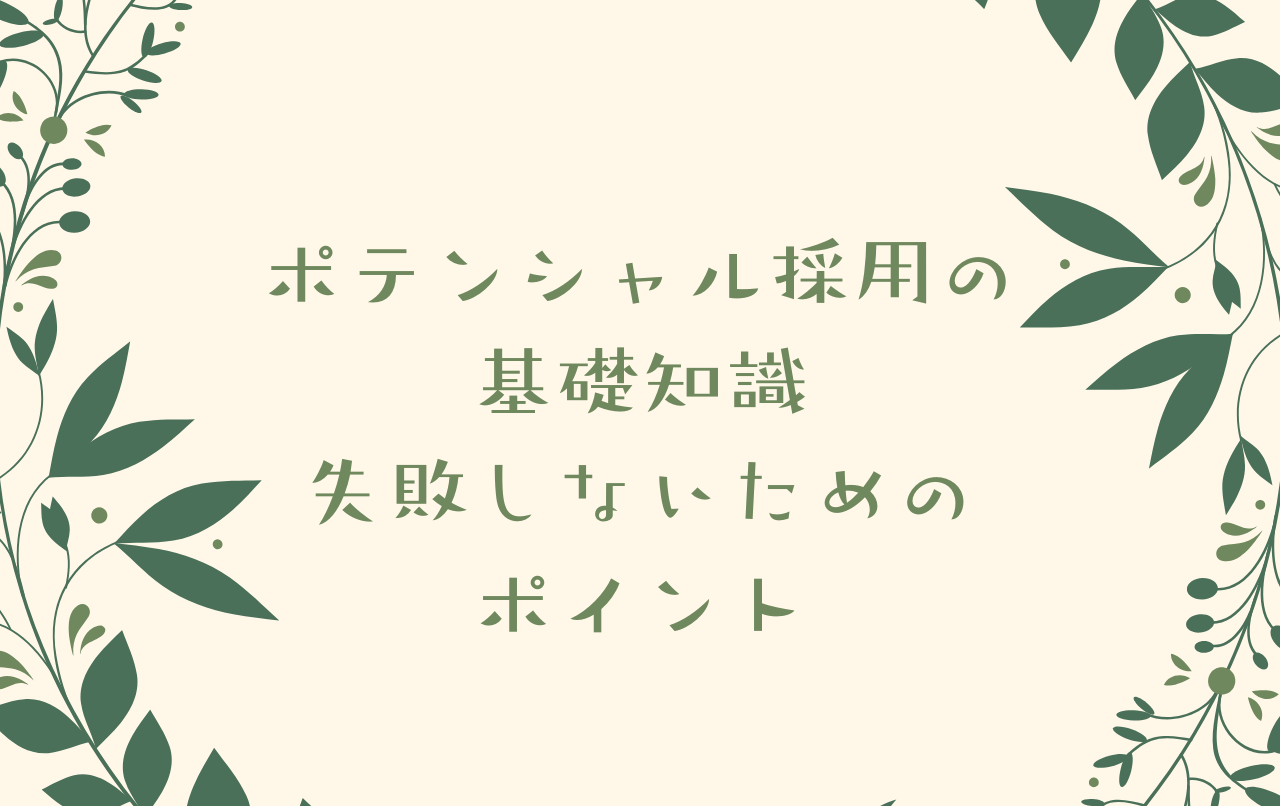
昨今、新卒採用だけでは若年層を採りきれず、加えて中途ならば経験者の採用がしたいという会社が多く、年々社内の平均年齢が上昇してしまうという事例がございます。
多くの会社は、そんな現状を打破するために、中途採用とは別に、第二新卒や未経験歓迎採用といった「ポテンシャル採用」に乗り出しています。
本記事ではポテンシャル採用を行う上でのメリットやポイントを提示しております。
「現状人手が足りている」といった場合でも、ポテンシャル採用を行わない場合に起こりうる問題点もご紹介しておりますのでご参考にいただけますと幸いです。
目次
ポテンシャル採用とキャリア採用の違い
ポテンシャル採用とは
まず、ポテンシャル採用は未経験採用とほぼ同義で使用されることが多いです。
ポテンシャル採用は下記のような定義付けがなされています。
ポテンシャル採用とは、応募者の現在のスキルや経験よりも潜在的な能力(ポテンシャル)や将来性を重視して行う採用手法のことです。
主に新卒人材や第二新卒、若手人材を対象に、中長期的な視点で成長や活躍が期待できる人材を見極める採用方法となっております。
具体的に言うと即戦力ではなく、入社後に育成することで企業に貢献できる可能性を評価基準とします。
例えば、業務経験がなくても、学習意欲、チャレンジ精神、人柄、適応力、コミュニケーション能力など、将来的に伸びしろのある要素が重視されます。
特に人材不足が課題となっている業界や、企業文化に合う人材を長期的に育てたい企業でポテンシャル採用が注目されています。
また、「現状人手が足りているから」とポテンシャル採用を行わないと、短期的には業務が回るかもしれませんが、長期的には「人材の枯渇」「柔軟性の低下」「コスト増大」といった問題が顕在化し、企業の成長が停滞するリスクが高まります。
加えて、人材が即戦力一辺倒になると、企業文化が硬直化し、「今までのやり方」に固執してしまう場合もございます。
ポテンシャル採用において未経験転職者や若年層を流入させることは企業にとって不可欠なな要素になってきています。もちろん新卒採用もポテンシャル採用の一環ですが、最近は第二新卒やヤングキャリアといった若年層重視、もっと言うなら「教育前提」の採用が活発化しています。
キャリア採用
一般的にキャリア採用は経験者採用とほぼ同義で使用されます。
キャリア採用のみでも良いかどうかについては、採用状況によります。
例えば、製造業の企業が「即戦力採用(キャリア採用)のみに頼った結果、熟練工ばかりを採用し続けたが、新技術への対応が遅れ、若手技術者が育たなかった。
その後、熟練工が退職し始めると技術継承が途絶え、生産力が落ちて競合他社にシェアを奪われた」という事例があります。
つまり、人材が不足していない状況でも、ポテンシャル採用は「未来への投資」として大いに意味を持ちます。イノベーション、コスト効率、組織の持続的成長を考えると、人材が安定している今だからこそ、余裕を持って次世代人材を育てられるチャンスとも言えます。
ポテンシャル採用の定義
ポテンシャル採用の年齢の定義については「ない」というのが答えとなります。
ポテンシャル採用は新卒や第二新卒といった若年層向けの求人のことを指し、中途採用と違って実績よりも相手の成長性に重きを置いた採用方法を指します。
「未経験でも育てられるか」「長期的に貢献できるか」を重視するため、理論上は年齢に厳格な上限はなく、重要なのは、応募者の「学習意欲」「柔軟性」「適応力」であり、これらがあれば30代、40代でも対象になり得ます。
以下は、一般的なポテンシャル採用におけるターゲット層の一覧です。参考にされてみてください。
【一般的なポテンシャル採用のターゲット層】
- 新卒(20代前半):
日本では新卒採用がポテンシャル採用の典型で、主に22~25歳が中心。
- 第二新卒(20代中盤~後半):
25~29歳頃。社会経験が浅く、柔軟性や成長余地が大きいと見なされる。 - 若手転職者(30代前半):
28~35歳程度。異業種からの転身やキャリアチェンジを希望する層で、意欲があればポテンシャル採用の対象に。 - 傾向: 多くの企業が「35歳くらいまで」をポテンシャル採用の目安とするケースが多い。これは、育成期間(3~5年)を経て40歳前後でリーダーシップを発揮することを想定しているため。
35歳以上をポテンシャル採用の人材とみなす会社は事実少なく、35歳を超えてきた人材は「即戦力採用」としての期待が高まります。
各年代のポテンシャル採用でのメリットと課題点
ポテンシャル採用での採用ターゲットとなる年代のメリットと課題点を下記にまとめております。
【20代(新卒・第二新卒)】
メリット: 柔軟性が高く、企業文化に馴染みやすい。育成期間を長く取れる。
課題点: 実務経験が乏しく、初期の教育コストが大きい。
【30代前半】
メリット: 社会経験がありつつ、成長余地も残る。即戦力とポテンシャルのバランスが良い。
課題点: キャリアの方向性が定まりつつあり、ミスマッチのリスクがやや増加。
【30代後半~40代】
メリット: 人生経験やソフトスキル(協調性、リーダーシップ)が活かせる。
課題点: 体力や学習スピードの低下を懸念される。企業側が「投資回収期間」を短く見積もる傾向。
企業側の視点でのポテンシャル採用での年齢上限
育成期間と投資回収
企業はポテンシャル採用で「5~10年後に成果を出す」ことを期待するため、30代半ば(35歳前後)が一つの目安。ただし、業界や職種により異なる。
例: IT業界は変化が速く、40代でも適応力次第で採用。製造業は体力面から若手を優先する傾向。
・法定年齢制限の禁止: 日本では「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」や「労働基準法」により、求人での年齢制限は原則禁止。ただし、企業の採用方針で暗黙の目安が存在する場合もある。
新卒中途問わず、「即戦力」の対義語にあたるのがポテンシャル採用となります。
転職者へのスキルより「成長性」を見据えた採用方法がポテンシャル採用のため「何歳まで」といった明確な年齢の定義がないのが答えとなります。
ポテンシャル採用の進め方とフローのポイント
ポテンシャル採用の進め方とフローについてまとめております。
気を付けるポイントについても記載しているのでご参考にいただけますと幸いです。
採用目標と評価基準の設定
まず初めに、なぜポテンシャル採用を行うのか目的を明確にします。「若手の育成」なのか「新規事業への投資」なのか経営課題を基に設定するのがよいでしょう。
そのうえで、ポテンシャル採用における自社の評価ポイントを決めていきます。「企業が求めるポテンシャルとは何か」「企業と合う価値観はどのようなものか」「企業が注目する素養、能力にはどのようなものがあるのか」といったものです。
自社が、ポテンシャル採用において対象者にどのような資質があることを求めていて、将来どんな活躍を期待しているのかを明確にしておくことが大切です。また、それらの基準を明文化しておくことも重要となります。
このような採用ペルソナの設定は、即戦力採用ではない分「スキル・経験」が決め手にならない為、非常に重要になってきます。ポテンシャル採用を行う上で経歴からも人物像の見極めは可能ですが、そのさらに奥の「人柄」についてまで考えて採用ペルソナを設定すると良いでしょう。
採用ペルソナの設定については、下記記事でもご紹介させていただいております。
ご興味あれば参考にされてみてください。
【テンプレート付】欲しい人材を確実に採る為の採用ペルソナ設定方法
選考プロセスの設計
採用目標と評価基準が決定したら選考プロセスの構築を行います。
新卒採用に近い「人間力」を図るものですので、ポテンシャルを見極める質問を用意して、いままでの経験よりも「プロセスや意欲」を評価する選考を行うことが重要です。
ポテンシャル採用で用いられる選考プロセス
・面接:
行動面接やケース面接を通じて、応募者の思考プロセスや対応力を評価する
(例:「困難な状況をどう乗り越えたか?」などの質問)
・ グループディスカッション:
協調性やリーダーシップ、創造性を観察する。
・ 適性検査:
性格や潜在能力を測るツールを活用し、客観的なデータを得る。
特にポテンシャル採用での面接で重要なのは、スキルではなくその人柄です。
そのため、その人物像がわかる質問をいくつか用意しておくと良いでしょう。
ポテンシャル採用は「採用で終わり」ではなく、「育成までがセット」のプロセスです。
つまずきを防ぐには、事前の準備(基準設定、育成計画)と、現場との連携が不可欠。
特に中小企業ではリソースが限られるため、外部の研修サービスやツール(適性検査など)を活用するのが有効となります。
採用決定とオンボーディング(育成計画)
採用を決める際は、複数の視点(採用担当、現場社員)で総合的に判断することを意識すつと良いでしょう。また、採用が決まった求職者には、入社する前に入社後の育成計画を事前に提示し、不安を軽減することも重要です。
また、育成は一朝一夕で終わるものではありません。未経験者ゆえに失敗もあるでしょう。そんな時にフォローアップしていく体制、環境を整えることも必要となってきます。
育成とフォローアップ
実際に入社された際は、研修やOJT、メンター制度を通じて実務スキルを習得させていきます。もちろん初めてなので「わからなくて当然」です。会社全体でそれを当たり前に受け入れられる体制の構築を目指すため事前に共通認識を持つと良いでしょう。
また、定期的な1on1やフィードバックでモチベーションを維持させ、成長を実感できる環境を整備することは、定着率を高めるために効果的な手法です。
ポテンシャル採用で気を付けたいポイント
【評価基準が曖昧】
問題: 「ポテンシャル」をどう測るか定まらず、主観的な判断になりがち。
例: 「この人は良さそう」と感覚で決めてしまい、後でミスマッチが発覚。
対策:
具体的な評価項目(例:問題解決力、コミュニケーション力)をスコア化し、
チームで共有。適性テストやケーススタディを活用して客観性を確保。
【育成体制の不足】
問題: 採用後に放置され、期待した成長が得られない。
例: 研修が不十分で、未経験者が業務についていけず早期離職。
対策:
入社後3~6か月の育成プログラム(研修+OJT)を設計。
メンターやサポート担当を配置し、進捗をモニタリング。
【即戦力への期待が残る】
問題:「すぐに結果を出してほしい」と求め、ポテンシャル採用の意義が薄れる。
例: 未経験者を採用したのに、初日から高いパフォーマンスを期待され不満が募る。
対策:
企業と現場の間で「長期投資」という認識を統一。
採用前に育成期間の必要性を説明し、期待値を調整。
【応募者のモチベーション維持が難しい】
問題: 未経験者ゆえに不安が強く、選考中や入社後にモチベーションが下がる。
例: 「自分に務まるか」と不安になり、内定を辞退。
対策: 選考中から丁寧なコミュニケーション(フィードバックや質問対応)を行い、入社後のキャリアパスを具体的に提示。
【成果が見えるまでの時間が長い】
問題: ポテンシャル採用は即効性がないため、経営層や現場から疑問視される。
例: 1年経っても成果が上がらず、「失敗だった」と判断される。
対策: 中間目標(例:3か月で基本スキル習得)を設定し、小さな成功を可視化。
長期的なROI(投資対効果)をデータで示す。
【ミスマッチのリスク】
問題: ポテンシャルを見誤り、企業文化や業務に合わない人材を採用してしまう。
例: 意欲は高いが協調性が欠け、チームに馴染めない。
対策: 選考で価値観や性格を深掘り(例:グループワークで観察)。
試用期間を活用して適合性を再確認。
ポテンシャル採用を行うメリット
①長期的な人材育成と競争力の強化
未経験者や若手を採用して育成することで、将来のキーパーソンやリーダーを自社で育てられることが大きな強みとなります。外部から高コストで即戦力を採用する必要性を減らし、自社のニーズに合った人材を長期的に確保できるため全社の活性化の大きく貢献が期待できます。
②ポテンシャル採用による長期的視点での費用対効果
即戦力人材と比較して、ポテンシャル採用では初期の人件費を抑えながら、入社後の育成を通じて将来的な費用対効果の向上が期待できます。
オンボーディングや継続的なフォローアップ体制をしっかり整備すれば、採用・育成にかかる総コストを含めても、長期的には即戦力採用よりもコストを抑えられる可能性があります。
③イノベーションと新しい視点の導入
未経験者層や若手層の採用は、従来の枠組みにとらわれない新しい視点や柔軟な発想を組織にもたらします。
これにより、社内に多様な価値観や思考が取り込まれ、組織の硬直化を防ぎ、市場の変化や技術革新にも柔軟に対応しやすくなるというメリットもあります。
④企業文化への適合性と定着率の向上
未経験者の採用は、単に人材を補充するだけでなく、既存社員にとってもメンターやリーダーとしての経験を積む機会となり、マネジメントスキルの向上や「ビジョン」の社内浸透を促進します。
その結果、社員のモチベーション向上や組織全体の活性化が期待できるほか、未経験人材は即戦力人材と比べて入社後のミスマッチが少なく、長期的な定着が見込める点も大きなメリットです。
こうした要素が積み重なることで、最終的には企業全体の成果向上にもつながります。
⑤採用競争の回避
実は見落とされがちなメリットの一つが、「ポテンシャル採用は即戦力人材と比べて採用競争が穏やかである」という点です。
即戦力人材は多くの企業が求めるため、争奪戦が激化しがちです。しかし、ポテンシャル層であれば、競合を避けやすくなります。
その結果、採用難易度が下がり、優秀な潜在能力を持つ人材を戦略的に確保しやすくなります。特に中小企業やスタートアップ企業にとっては、限られたリソースの中でも成果につながる採用が実現しやすいアプローチと言えるでしょう。
ポテンシャル採用の失敗事例から見るデメリットと改善点
ポテンシャル採用を行うことによるメリットについては前章までで紹介させていただきました。しかし、ポテンシャル採用もメリットばかりではございません。
本章では「起こりうる失敗例」をご紹介いたします。いずれも予防策と改善点をしっかりと抑えておくことで採用成功につなげることが可能です。
失敗事例1: 人材の見極めミスによる転職者の早期離職
- 事例: ある中小IT企業が、20代の未経験転職者をポテンシャル採用で積極的に採用。選考では「やる気」や「コミュニケーション力」を重視したが、具体的な評価基準が曖昧だった。入社後、採用した人材が業務の難易度に適応できず、半年以内に半数以上が退職。
- 原因:
- ポテンシャル採用の定義が不明確で、面接官の主観に依存してしまった。
- 業務内容や必要な適性(例: 論理的思考力、忍耐力)を事前に伝えず、ミスマッチが発生。
- 改善点:
- 評価基準の明確化: 転職者の「学習意欲」を測るなら「過去に自己学習した経験」を聞くなど、具体的な質問とスコアリングを導入。
- 現実的な期待設定: 求人広告や面接で業務の厳しさや育成期間を正直に伝え、転職者へ覚悟を確認。
- 試用期間の活用: 3か月の試用期間で適性を再評価し、ミスマッチを早期発見。
失敗事例2: ポテンシャル採用を行った後の育成体制不足による成長停滞
- 事例: 地方の製造業が、若手技術者をポテンシャル採用で入社させた。未経験の転職者でも「ものづくりへの情熱」を重視したが、入社後の研修が現場任せで体系的でなく、1年経ってもスキルが身につかず、ポテンシャル採用で入社した社員のモチベーションが低下。
- 原因:
- ポテンシャル採用後の育成計画が不十分で、OJTが「放置」に近い状態に。
- 現場が転職者に対して即戦力を期待し、育成に協力しない姿勢。
- 改善点:
- 育成プログラムの設計: 入社後3か月の基礎研修やメンター制度を導入し、成長をサポート。
- 現場との連携: 採用前に経営層と現場で「育成に時間がかかる」ことを共有し、ポテンシャル採用における期待値を調整。
- 進捗管理: 定期的な1on1面談で成長度合いを確認し、転職者へのモチベーション向上につなげ、企業の軌道修正。
失敗事例3: 応募者が集まらず採用活動が停滞
- 事例: 小売チェーンがポテンシャル採用を掲げて求人広告を出したが、知名度が低く「未経験歓迎」だけでは魅力が伝わらず、応募がほとんど集まらなかった。広告費だけがかさみ、採用に至らず。
- 原因:
- 企業の魅力(ビジョン、育成環境)が伝わらない求人内容。
- 大手企業との競争で埋もれる。
- 改善点:
- 求人内容の強化: 「入社3年で店長になった事例」「充実した研修制度」など具体的な成功ストーリーを記載。
- ターゲットに合った媒体: 若手が使うSNS(例: Instagram、Twitter)で発信し、カジュアルなトーンでアピール。
- 低コストから開始: 無料の求人サイトや社員紹介(リファラル)を活用し、効果を見極めてから予算投入。
失敗事例4: 企業文化とのミスマッチ
- 事例: 広告代理店がクリエイティブな若手をポテンシャル採用で採用。選考では「アイデア力」を重視したが、入社後、企業のトップダウン文化に馴染めず、主体性を発揮できずに退職者が続出。
- 原因:
- カルチャーフィットを見極める質問やプロセスが不足。
- 応募者に企業風土を十分伝えなかった。
- 改善点:
- 価値観の確認: 面接で「どんな環境で働きたいか」「過去のチーム経験」を聞き、風土との適合性を評価。
- 透明性: 求人や面談で「上下関係が明確」「スピード重視」などの文化を明示。
- 双方向の対話: カジュアル面談で応募者からも質問を受け、相互理解を深める。
失敗事例5: 経営層と現場の認識齟齬
- 事例: 大手サービス業がポテンシャル採用を導入したが、経営層は「未来のリーダー育成」を目指した一方、現場は「すぐに成果を出してほしい」と期待。結果、新入社員へのサポートが不足し、不満が広がり退職率が上昇。
- 原因:
- 採用目的が全社で共有されていなかった。
- 現場が育成負担を過大に感じた。
- 改善点:
- 事前調整: 採用前に経営層と現場で「育成に3年かかる」などの目標を合意。
- インセンティブ: 育成に協力する現場社員に報奨金や評価ポイントを付与。
- 成果の可視化: 小さな成長(例: 基本スキル習得)を共有し、現場のモチベーションを維持。
共通する失敗要因と改善の方向性
- 見極めの難しさ: ポテンシャルは定量化しづらいため、主観的な判断で失敗しやすい。
- 改善: 適性テストやグループワークで客観データを収集。
- 育成の欠如: 採用後のフォローが不十分だと、ポテンシャルが開花しない。
- 改善: 体系的な育成計画と定期的なフィードバックを確立。
- 期待のズレ: 企業と応募者、現場との認識が一致しない。
- 改善: 採用プロセスで透明性を保ち、全員の理解を揃える。
ポテンシャル採用の失敗事例は、見極め基準の曖昧さ、育成体制の不足、コミュニケーション不足に起因するものが多いです。改善するには、採用前の準備(基準設定、現場調整)、採用時の透明性(期待の明確化)、採用後のサポート(育成計画)を徹底することが不可欠です。これらを踏まえれば、失敗リスクを減らし、ポテンシャル採用のメリットを最大化できます。
ポテンシャル採用の手法
本章ではポテンシャル採用の手法をご紹介させていただきます。
状況に合わせ下記手法を取り入れる
①インターンシップやワークショップを開催する
主に新卒に向けて短期のインターンシップや体験型プログラムを通じて、候補者の適性や意欲を直接観察する手法です。1日~数週間のインターンを開催することで、実践的な課題を通じてポテンシャルを評価でき、求職者への入社意欲も高められるメリットがあります。
もし行う場合はスキルよりもプロセス(協調性、創造性)を重視した評価基準を設けることを意識すると良いでしょう。
参加者の中から優秀者をスカウトすることや、インターン参加者へ「採用フローの飛び級提案(1次面接免除など)」もできるため、非常に効率的な手法と言えます。
しかし、インターンシップやワークショップを導入する場合、いくつか気をつけるべきポイントがあります。
第一に、新卒採用以外への適用は非常に難しいという点です。特に、すでに働いている第二新卒以上の人材を集めるのは現実的ではありません。そのため、中途採用向けにこの手法を使おうとしても、あまり効果は期待できません。
次に、企業の知名度が応募数に大きく影響する点も注意が必要です。知名度の高い大手企業であれば応募が集まりやすいですが、知名度が低い中小企業の場合は、そもそも応募者が集まらないことも多く、あまり効果的とは言えません。
そのため、インターンシップやワークショップは企業の規模や目的に応じて、慎重に導入を検討する必要があります。
②SNSやオンラインツールの活用
近年は、XやWantedly、LinkedInなどを通じて、ポテンシャル人材に直接アプローチする企業が増えています。
「DMによって直接やり取りできる」ことに加え、若手や転職潜在層にリーチしやすく、企業ビジョンを伝えやすいのがメリットとなっています。
しかし、この手法は手軽でコストも抑えられるというメリットがありますが、いくつかの注意点もあります。
まず、利用者全員が必ずしもに積極的とは限らないため、企業側はカジュアルなトーンで自社の魅力を伝えること、そして双方向の対話を重視することが重要です。
その反面、「無効応募(選考意欲の低い応募)」が増える可能性もあり、結果として選考効率が下がるリスクがあります。また、定期的に社外への広報活動を行う必要があるため、タスクの増加や対応リソースの確保も求められます。
このような点から、ポテンシャル採用の主力手法として活用するのは難しいと言わざるを得ません。あくまで補助的な位置づけとして、他の手法と併用する形で取り入れるのが現実的です。
③人材紹介会社やエージェントとの連携
ポテンシャル採用を丸ごと人材紹介会社に任せるケースもあります。人材紹介会社に「ポテンシャル重視」の採用ニーズを伝え、未経験者や第二新卒を紹介してもらう手法です。
この方法の最大のメリットは、プロの目で適性のある候補者をしっかりスクリーニングしてもらえるため、ミスマッチが起きにくいことです。さらに、キャリアアドバイザー(CA)やリクルーティングアドバイザー(RA)を介しているため、質の高い求職者を紹介してもらえる可能性が高いのも魅力です。
一方で、デメリットとしては紹介手数料が高額なことが挙げられます。相場は年収の30~35%ほどで、ポテンシャル採用の費用対効果としては割に合わない場合もあります。また、エージェント側の理解不足で「ポテンシャル重視」という意図が正しく伝わらず、即戦力の人材を提案されるリスクもあります。
人材紹介会社を活用する際は、「学習意欲」や「柔軟性」、「何歳までの候補者か」といった条件をしっかり明確に伝えることが成功のポイントです。
④リファラル採用(社員紹介)
リファラル採用は近年注目されている採用手法の一つです。
既存社員から知人や友人を推薦してもらい、ポテンシャルの高い人材を発掘する手法です。社員が企業文化や業務内容を理解した上で紹介するため、採用後のミスマッチが少なく、信頼性の高い採用が期待できます。また、人材紹介会社を利用する場合と比較して採用コストを抑えられる点も大きなメリットです。費用対効果の観点からも非常に有効な採用手法と言えます。
一方で、社員の交友関係に依存するため、多様性の確保が難しくなりがちであることや、社員数が少ない場合には紹介数が限定される点はデメリットとして考慮が必要です。リファラル採用に過度に依存すると人材の偏りが生じる可能性があるため、採用チャネルの一つとして位置付け、補完的に活用することが望ましいと考えます。
加えて、リファラル採用の成功には社員が紹介しやすい環境整備やインセンティブ設計が重要です。紹介制度の運用方法や周知方法を工夫することで、より良質な人材の獲得につなげることが可能となります。
⑤求人広告掲載によるポテンシャル採用求人の打ち出し
求人広告は、費用対効果が高く、ポテンシャル採用のメインとしても非常に有効です。
広範な人材層にアプローチできるうえ、ポテンシャル層の採用に適しているため、採用競争を回避しやすい点がメリットです。また、応募者の意欲を把握しやすく、ミスマッチのリスクを低減できることも大きな強みです。
ただし、求人原稿の内容によって応募者の質にばらつきが生じるため注意が必要です。
募集条件を緩めすぎると選考工数が増え、逆に厳格すぎると母集団形成が困難になる可能性があります。そのため、一部企業では広告内に「なぜ当社で働きたいか」といった簡単な質問を設け、応募者の意欲を事前に確認するといったような工夫が必要となってきます。
ポテンシャル採用:効果的な求人広告の掲載方法
- ターゲットを明確に訴求するメッセージ
- 方法: 「未経験歓迎」「成長意欲を重視」「スキルより人柄」といったキーワードを使い、ポテンシャル層に刺さるメッセージを強調。
- 例: 「経験ゼロからプロへ!あなたの挑戦を応援します」「スキルは入社後に教えます、やる気があればOK」
- ポイント: 若手や異業種転職者が「自分でも応募できる」と感じる文言を選ぶ。
- 企業のビジョンや育成環境をアピール
- 方法: 自社のミッションや長期的な成長支援(研修、OJT、メンター制度)を具体的に記載。
- 例: 「10年後のリーダー候補を募集」「入社後3か月の研修でしっかりサポート」
- ポイント: ポテンシャル採用は「未来への投資」なので、入社後のキャリアパスをイメージさせ、不安を軽減。
- 多様な媒体を活用
- 求人サイト: Indeed、マイナビ転職、リクナビ(新卒向け)など、幅広い層にリーチ。
- SNS: Twitter(X)、Instagram、LinkedInでカジュアルに発信。
- 自社サイト: 採用ページにポテンシャル採用の特設コーナーを設ける。
- ポイント: 若手はSNSやモバイルで求人を探す傾向が強いため、媒体を分散。
- 応募へのハードルを下げる
- 方法: 履歴書不要やカジュアル面談の案内を明記し、応募の心理的障壁を減らす。
- 例: 「まずは話してみませんか?履歴書なしでOK」「応募前に質問歓迎」
- ポイント: 未経験者は応募に躊躇しがちなので、気軽さを強調。
- 具体的な成功事例を盛り込む
- 方法: ポテンシャル採用で入社した社員の成長ストーリーを紹介。
- 例: 「入社時未経験だったAさんが3年で店長に!」「新卒からプロジェクトリーダーに成長」
- ポイント: 具体性が信頼感を生み、応募意欲を高める。
- ビジュアルや動画を活用
- 方法: 写真や動画で職場の雰囲気、社員の声、研修風景を伝える。
- 例: 若手社員が「成長を実感できる職場」と語るショート動画を添付。
- ポイント: 若い世代は視覚情報に反応しやすい。
- ターゲットを明確に訴求するメッセージ
ポテンシャル採用においては、求人広告、インターンシップ、SNS、リファラルなど、従来の経験者採用とは異なるチャネルが有効です。採用効率を高めるためには、企業が求めるポテンシャルの定義を明確化し、それに適した手法を選択することが重要となります。
大企業はリソースが豊富なため、求人広告やインターンシップ、外部提携を活用することで効率的な採用が可能です。一方、中小企業では、SNSやリファラルの活用が低コストかつ効果的な手段と言えます。
特にポテンシャル採用向けの求人広告は、「明確なメッセージ発信」「育成環境の訴求」「多様な媒体の活用」によって効果を最大化できます。幅広いリーチや採用競争の回避、企業ブランディング向上といったメリットがある一方で、応募者の質のばらつきや育成負担増加といった課題にも留意が必要です。広告掲載に先立ち育成体制を整備し、ターゲット層に響く内容を工夫することで、効率的かつ効果的な採用活動を実現できます。
ポテンシャル採用の基礎知識、失敗しないためのポイント まとめ
ポテンシャル採用の基礎知識、失敗しないためのポイントをご紹介させていただきました。
ポテンシャル採用は、即戦力に頼らず、成長意欲や柔軟性を持つ若手人材を見つけて長期的に育成する戦略的な採用方法です。これにより、企業は自社文化にマッチし、将来的に高いパフォーマンスを発揮できる人材を確保できます。一方で、適切な評価基準と育成体制がないと早期離職や成長停滞のリスクがあるため、採用プロセスと育成計画の継続的な見直しが成功の鍵となります。
求人広告代理店である株式会社bサーチは、中途採用の広告支援(dodaやマイナビ、Indeed)の取り扱いだけでなく、ポテンシャル採用における課題解決もサポートします。
これまでの実績、ノウハウを駆使し採用のお手伝いをさせていただきます。
採用活動に関してお困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

