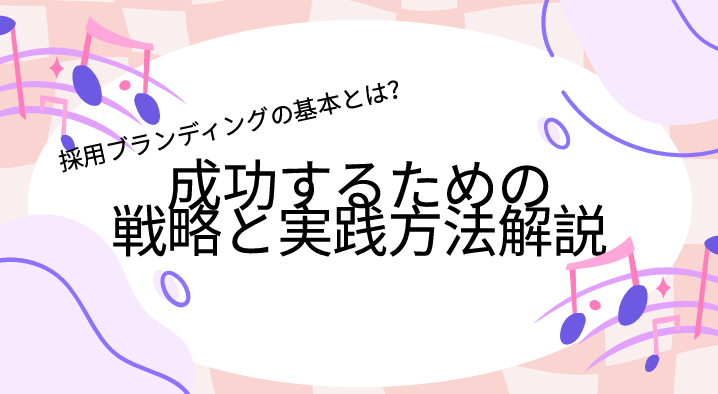
採用活動がうまくいかない――そんな悩みを解決するカギが「採用ブランディング」です。単に人を集めるのではなく、求職者に対して企業文化や情報を発信することで自社の魅力を明確に伝え、より企業とマッチした人材を採用できるため、結果的に定着率向上、コスト削減につながります。
「採用ブランディングって興味があるけどやり方がわからない」
「名前は知ってるけど、そもそも採用ブランディングって何から取り組めばいいの??」
「定着率を上げるにはいったいどうすれば…」
この記事では、採用ブランディングの基本や進め方、実際の改善事例までをわかりやすく解説します。自社に合った人材を採用し、定着率を高めたい方は、ぜひご一読ください。
採用ブランディングの目的・方法について
採用ブランディングとは、『企業が雇用主としての魅力を定義し、それを社内外に効果的に発信することで、求職者や社員に「この会社で働きたい」「この会社で働き続けたい」と思わせるプロセス』です。マーケティングの「ブランド構築」と似た概念ですが、ターゲットは主に求職者や現社員であり、企業の「働く環境」や「価値観」を中心に訴求します。
採用ブランディングは、以下の2つの側面を持つことが一般的です。
・外部ブランディング:求職者や市場に対して、企業を魅力的な職場としてアピールする。
・内部ブランディング:現社員に対して、企業文化や価値観を強化し、満足度やエンゲージメントを高める。
これらの情報について、企業情報の発信のほかにも下記で挙げるような「人材獲得と組織全体の成長をサポートする」という目的があります。
①優秀な人材の獲得
競争の激しい人材市場で、スキルや価値観がマッチする候補者を引きつけられます。
特に、転職活動中のアクティブな求職者だけでなく、良い機会があれば転職を考えているパッシブな候補者にもアピールすることができるのが強みです。
採用ブランディングを通じて長期的な認知を築くことで、採用後のミスマッチを減らし、長期的な貢献を期待できます。
②採用コストの削減
採用ブランディングに着手することで強力なブランドイメージを策定できれば、広告費やリクルーターの負担が減り、候補者が自然に集まるようになります。一度ブランドが確立されると、求職者が自ら企業のウェブサイトやSNSを訪れ、応募する傾向が高まります。さらに、ブランドへの信頼がある応募者は、選考プロセスでの離脱率が低く、採用までの時間が短縮される側面もあるため、採用プロセスの効率化にも寄与されます。
③社員の定着率向上
魅力的な職場環境をアピールすることで、現社員にも影響を与えられます。企業の価値観、文化、ミッションを明確に発信することで、社員が「この会社で働く意義」を再認識し、誇りやモチベーションが高まります。 ワークライフバランスや成長機会が実際の職場環境と一致している場合、社員の信頼感が増し、長期的な定着が促される可能性もございます。
④企業ブランドの強化
採用ブランディングは、顧客向けのブランドイメージとも連動し、企業全体の信頼性や魅力を高める効果もあります!ポジティブな雇用主ブランドは、口コミサイトやSNSでの評判を高め、企業の社会的信頼を強化できるため、環境意識の高い顧客や投資家からも支持を得られる可能性も秘めています。
⑤求職者体験の向上
採用プロセスでのポジティブな体験を提供することで、求職者に信頼感を与えることができます。特に、この結果不採用となった候補者でも、良い体験があれば、SNSや口コミサイトで企業を肯定的に評価する可能性が高く、採用ブランディングを通じて、企業の「人間性」や「誠実さ」を伝えることで、求職者のエンゲージメントが向上する利点もあります。
このように採用ブランディングによって、ブランドイメージを定着させれば、自然と求職者が集まり、よい口コミを発信し、さらなるブランドイメージの向上…といったサイクルを回せる状態にすることが、採用ブランディングを行う本質とも言えます。
採用ブランディングと採用広報の違い
採用ブランディングと採用広報は、どちらも企業の採用活動において重要な役割を果たします。しかし、目的、範囲、焦点において明確な違いがあります。
採用ブランディング
定義: 企業が雇用主としての魅力や価値を定義し、求職者や現社員に対して「ここで働きたい」「ここで働き続けたい」と思わせるブランドイメージを構築する戦略的なプロセス。
焦点: 長期的なブランド構築。企業の文化、ミッション、働く環境、価値観を一貫して伝え、求職者や社員との信頼関係を築く。
例: 企業文化を伝える社員インタビュー動画の公開、キャリアページでのEVP(Employee Value Proposition…企業が従業員に提供する価値)の訴求、SNSでの職場環境の発信。
採用広報
定義: 採用活動の一環として、求人情報や企業の魅力を具体的なターゲット(求職者)に伝え、応募を促進するためのコミュニケーション活動。
焦点: 短期~中期的な採用目標の達成。特定の求人や採用キャンペーンを広く周知し、候補者を集める。
例: 求人広告の掲載、採用イベントの告知、WantedlyやLinkedInでの求人投稿、説明会の開催。
つまり、長期的な採用サイクルを作成するためのブランドイメージを向上させるための発信が「採用ブランディング」、採用活動の一環で短期的に募集を集めるための方法が「採用広報」となります。
| 採用ブランディング | 採用広報 |
目的 | 雇用主としてのブランドを構築し、長期的に優秀な人材を惹きつけ、定着させる。 | 特定の求人や採用キャンペーンを周知し、短期~中期的に応募者を集める。 |
時間軸 | 長期視点(数ヶ月~数年)。ブランドの信頼性や認知度を徐々に高める。 | 短期~中期視点(数週間~数ヶ月)。特定の採用ニーズに対応。 |
対象 | 求職者(潜在的候補者を含む)、現社員、場合によっては顧客や一般市場。 | 主にアクティブな求職者(現在仕事を探している人)。 |
焦点 | 企業文化、価値観、EVP、職場環境など、企業の「本質」を伝える。 | 求人内容、職務内容、応募方法、採用イベントなど、具体的な情報を伝える。 |
活動例 | – 社員のストーリー動画 | – 求人広告の作成・配信 |
成果指標 | – ブランド認知度 | – 応募者数 |
アプローチ | 戦略的・包括的。企業のミッションやビジョンと連動し、一貫性のあるメッセージを発信。 | 戦術的・具体的。特定の職種や採用目標に合わせて、ターゲットに直接訴求。 |
※DEI…Diversity(ダイバーシティ、多様性)、Equity(エクイティ、公平性)、Inclusion(インクルージョン、包括性)の頭文字を組み合わせた言葉で、企業経営において、多様な人材を尊重し、公平な機会を提供し、誰もが主体的に活躍できる環境を整備すること。
採用広報と採用ブランディングはどちらかが優れているというものではなく互いに補完し合う関係です。
①土台としての採用ブランディング
採用ブランディングは、企業がどのような職場かを明確に定義し、求職者に一貫したイメージを提供する「土台」です。強力なブランドがあれば、採用広報の効果が高まり、求人への反応が良くなります。
例: 採用ブランディングで「研修がしっかりとしている職場」をアピールしている企業は、求人広告で「過去不問・未経験者歓迎」と書くことで、信頼性のある訴求が可能。
②実行手段としての採用広報
採用広報は、採用ブランディングで構築したメッセージを具体的な採用活動に落とし込む「実行手段」です。ブランドの魅力を、求人情報やイベントを通じてターゲットに届ける役割を果たします。
例: 採用ブランディングで「成長機会の豊富さ」を訴求している企業が、採用広報で「入社後の研修制度」を強調した投稿をSNSに掲載する。
③フィードバックの循環
採用広報を通じて得た求職者の反応(例: 応募者の質問、口コミ)は、採用ブランディングの改善に役立つ。たとえば、求職者が「ワークライフバランス」に興味を示す場合、ブランディングでその点を強化する。
採用広報を続け、求職者の反応にこたえていくことで、企業のブランドイメージが向上し、採用ブランディングのさらなる効果向上が見込めます。
そういう意味で、採用ブランディングも採用広報もどちらも行っていく必要がございます。
どちらも続けていくことで、採用広報はより求職者の知りたい情報を発信でき、その結果ブランドイメージにつながります。
採用ブランディングの方法と進め方
本章では、具体的な採用ブランディングの進め方について解説いたします。
採用ブランディングは主に下記のの8ステップで実行されることが多く見られます。
①現状分析と目標設定
②ターゲット人材の定義
③EVPの策定
④ブランドメッセージとコンテンツの作成
⑤発信チャネルの選定と展開
⑥求職者体験の設計と最適化
⑦効果測定とKPIの追跡
⑧継続的な改善とブランディングの進化
1点ずつ解説させていただきます。
①会社の現状分析と目標設定
現状の採用課題やブランドの立ち位置を把握し、ブランディングの方向性と目標を明確にしていきます。
採用ブランディングを行う上で「訴求したい部分はどこか、会社のどこを補強していくか」を定めることは、よりよい訴求を行うために必須となってきます。
具体的なアクション内容
内部調査:
現社員にアンケートやインタビューを実施し、企業の強み、弱み、文化、満足度を把握
例: 「当社で働く魅力は何か?」「課題は?」。
外部調査:
求職者や競合他社の視点で自社の評判を分析。口コミサイト(例: OpenWork、Glassdoor)、SNSでの言及、競合のキャリアページをチェック。
採用データの分析:
過去の応募者数、採用率、離職率、応募者の動機を整理。
例:「応募者が少ないのは認知不足か、魅力の発信不足か?」。
目標設定:
SMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)基準で目標を設定。
例: 「6ヶ月で応募者数を30%増加」「1年でOpenWorkの評価を4.0以上に」。
社員の声やデータを軽視せず、リアルな課題を直視することで、現状の課題と向き合い払拭することはブランドイメージ向上につながります。
ここで行う要件定義が後々の採用ブランディングに活きてきます。もしうまくいかない場合や、別の課題が発生した際は、再度この項に立ち返ることも重要となります。
②ターゲット人材の定義
採用ブランディングの要件が定まったら、次は採用ブランディングを行う上でのターゲットと求職者層を明確化していきます。年齢や性別で、重視している点が異なるため、今回のブランディングにおいて訴求ポイントと訴求先を絞ることで、効果向上が見込めます。
具体的なアクション内容
ペルソナ作成: ターゲット人材の属性(年齢、職種、スキル、価値観)を詳細に設定。
例: 「25-35歳のエンジニア、成長機会とチームワークを重視」など。
動機の分析: ターゲット層が求める要素を調査(例: 給与、ワークライフバランス、社会貢献)。LinkedInやWantedlyのデータ、業界レポートを活用。
チャネル特定: ターゲットが情報収集する場所(例: X、LinkedIn、業界イベント)を特定。
ターゲット人材の定義を行う上で注意すべきなのは、訴求先を広げすぎないことです。
新卒求職者と中途採用者で求めているものが異なるように「訴求するポイントと訴求先」を可能な限り狭めていくことが成功への近道となります。
③EVPの策定
EVP(Employee Value Proposition)とは、「企業が従業員に提供する価値」の事です。
媒体やSNSを用いたブランドイメージ向上の施策の一つとして、企業が「独自の価値を定義し、競合他社との差別化を図る」ことが重要になってきます。
具体的なアクション
強みの整理:調査をもとに、企業の魅力(例: フラットな組織、学習支援、リモートワーク)を洗い出す。
差別化ポイントの明確化: 競合他社と比較し、独自の価値を特定。
例: 「業界トップクラスのメンター制度」「地域密着の社会貢献」。
EVPの言語化: 簡潔で共感を呼ぶメッセージを作成。
例: 「自由な働き方で、チームワークを最大化」
検証: 社員やターゲット人材にEVPをテストし、響くかどうかを確認。
EVPは実際の職場環境と一致させることを意識することが必要となります。
誇張表現は評価や信頼を失う可能性があるため、ありのままを伝えることが重要ですね。
社内調査で出た課題点に対し「最近社内ではこのような取り組みをしている」と発信して真摯に向き合うことで、社外のターゲットへの訴求だけでなく、社内のエンゲージメントを高める事に寄与します。
④ブランドメッセージとコンテンツページの作成
EVPを基に、求職者や社員に響く一貫したメッセージとコンテンツを開発して発信していきましょう。
具体的なアクション内容
メッセージ開発: EVPを簡潔なスローガンやキーフレーズに変換。
例: 「挑戦を応援する職場」「多様性が未来を創る」。
コンテンツ制作
社員ストーリー: 社員のインタビュー動画、ブログ
例: 「入社1年目の挑戦」「リモートワークの日常」
ビジュアル: オフィスやイベントの写真、インフォグラフィック
例: 「当社のDEI取り組み」
キャリアページ: ミッション、EVP、社員の声を掲載した専用ページを充実。
SNS投稿: X、LinkedIn、Instagramで定期的な発信
例: 社内イベント、社員の成果
ビジュアルの研究: ターゲットに合わせたトーンを設定(例: 若手向けはカジュアル、シニア向けは信頼感など)。
とにかくリアルな内容を発信することが大切です。求職者が見たい点はあくまでも「会社の中身」であるため、ありのままを発信し続けることを意識する必要があります。
⑤発信サイトの選定と求人展開施策
発信内容が定まったら施策の実施に移っていきます。
ブランディングコンテンツを効果的に届けるための方法をご紹介いたしますので、ご参考にしていただけますと幸いです。
具体的なアクション内容
自社チャネル:キャリアページをSEO最適化し、検索上位に表示。企業ブログで「働く環境」を定期更新。
SNS
LinkedIn: プロフェッショナル向けにキャリアストーリーや求人情報を発信。
X: リアルタイムで社内イベントやニュースを投稿。
Instagram: ビジュアル重視で職場環境や社員の日常を公開。
求人広告:Wantedly、Indeed、Greenで、EVPを反映した求人広告を掲載。
オフライン:業界イベント、大学でのセミナー、インターンシップを開催し、ハッカソンやコミュニティ活動で潜在候補者と接点を作る。
社員アンバサダー:社員にSNSで発信を促す
例: ハッシュタグキャンペーン「#私の職場」
施策を実施していくうえでターゲットに合わせて媒体を選ぶことが非常に重要となります。
各媒体で、それぞれ強みがある領域が異なるのでターゲットに合わせ媒体を選定することを心がけましょう。
⑥求職者体験の設計と最適化
採用プロセス全体でポジティブな体験を提供し、ブランドの信頼性を強化することは可能です。不採用であったとしてもブランドイメージの補強につながります!
具体的なアクション内容
応募プロセス:シンプルで分かりやすい応募フォームを用意。自動返信メールに温かみのあるメッセージを追加
例: 「あなたのご応募を楽しみにしてます!」
面接:面接官をトレーニングし、企業の価値観を伝える。また候補者の質問に丁寧に答えるように訓練。
フィードバック:不採用の場合も、建設的なフィードバックを提供。また、採用後のフォローアップで入社意欲を維持。
透明性:選考スケジュールや基準を事前に共有。
誠実な対応を心掛けることが必要となります。遅い対応や不明確な選考プロセスは、求職者に不誠実なだけでなくブランドイメージを深く傷つける危険性もございます。
⑦効果測定とKPIの追跡
あ採用ブランディングにおいて最も重要なのが「効果測定」です。
ブランディングの成果を定量・定性的に評価し、改善点を特定していきましょう。
具体的なアクション内容
定量KPI:応募者数、採用数、応募者1人当たりのコスト。ウェブサイトや求人広告のクリック率、SNSのエンゲージメント(いいね、シェア)。口コミサイトのスコア
定質KPI:
求職者アンケート 例:「当社の印象は?」
社員のエンゲージメント調査 例:「当社の文化に誇りを感じるか?」
データ分析:Google Analyticsでキャリアページのトラフィックを分析。応募者の属性や動機をCRMツールで追跡。
短期的な成果に偏らず、長期的な指標も重視することが必要となります。具体的に述べるならば、応募者数のみを判断材料とせず、定着率はどうか、口コミはどうかといった指標を確かめていく必要があります。特にここ最近では、口コミサイトの影響力は非常に強いため、定期的にモニタリングしていくのが大切なってきます。
⑧継続的な改善とブランディングの本格的な強化
採用ブランディングの最終的な目標は、ブランドイメージからサイクルを構築して採用サイクルを回すことです、そのため、採用ブランディングに終わりはありません。市場や求職者のニーズ変化に対応し、ブランディングを継続的に強化して発信し続けることが重要になってきます。
具体的なアクション内容
フィードバック収集:求職者や新入社員にブランディングの印象をヒアリング。社員の声を定期的に反映。
例: 社内イベントの公開
トレンド対応:DEI、リモートワーク、ESGなど、求職者が重視するテーマをブランディングに取り入れる。
例: 「カーボンニュートラルへの取り組み」を発信
コンテンツ更新:キャリアページやSNSを定期的にリフレッシュ。新しい社員ストーリーや成果を追加。
社内連携:人事、マーケティング、経営層が協力し、一貫したメッセージを維持。
新たな課題や採用を考えるとき、すでにあるブランドイメージが武器となります。
運用を行っていくうえで課題を感じた際は、再度要件定義を考えて動くことも重要です。
採用ブランディングを行う上での注意点
陥りがちな失敗例と改善方法
この項ではよくある失敗例と改善案を記載します。失敗例を先に知っておくことで、未然に防ぐことができます。
まずは失敗における共通原則をご紹介いたしますので、それを踏まえてご一読いただけますと幸いです。
失敗を防ぐための共通原則
誠実さと透明性: ブランディングは現実に基づき、誇張を避ける。社員や求職者の声を反映。
継続的な改善: 失敗を早期発見し、小さな調整を積み重ねる。例: 四半期ごとの口コミ分析。
社内巻き込み: 社員をブランディングのパートナーとし、信頼感を醸成。
データ駆動型アプローチ: 応募者データ、口コミスコア、エンゲージメント率を分析し、戦略を最適化。
①採用ブランディングで「ワークライフバランスを重視」「挑戦を応援する文化」と発信するが、実際には長時間労働や硬直した組織文化が常態化。社員が期待と現実のギャップに悩み、ネガティブな口コミの投稿が行われていた
【原因】
これは、採用ブランディングで発信していた内容と実際の職場環境にギャップが生じてしまったことが原因となります。
【解決策】
現状分析を徹底:ブランディング前に、社員アンケート(例: Google Formsで匿名実施)や1on1ミーティングで、実際の職場環境を把握しましょう!「うその情報」を発信しないように心がけることが重要です!
例: 「本当にワークライフバランスは取れているか?」
口コミサイト(OpenWork、Vorkers)を分析し、社員の不満を特定することも大事ですね!
現実的なEVPの設定:企業の強みを誇張せず、現実に基づいたEVP(Employee Value Proposition)を定義しましょう!非現実的だと求職者はかえって訝みます…。
例: 「毎週決まった曜日は難しいが、週2日のリモートワークを保証」
社員や経営層とEVPを検証し、実現可能性を確認するようにしましょう!実現可能でない目標は、かえってブランドイメージを落とす結果につながります。
職場改善を優先:当たり前ですが、ブランディングで発信する内容を、実際の制度や文化に反映するようにしましょう。
例: 残業削減のため、プロジェクト管理を改善。
継続的なフィードバック:社員や新入社員から定期的にフィードバックを収集し、ギャップを早期発見することも重要です!常に会社の情報を把握し続けることが重要ですよ!
例: 入社3ヶ月後のアンケートで「期待との違い」を確認。
長期視点の戦略立案:ブランディング計画を6ヶ月~1年単位で設計し、長い目で採用ブランディングをすることを心掛けましょう!
例: 「1年で口コミ評価を3.5から4.0に」「応募者数を20%増」。
短期KPI(例: 応募数)と長期KPI(例: 口コミスコア、定着率)をバランスよく設定して、比重が偏りすぎないようにしましょうね!
職場環境の基盤強化:ブランディング前に、社員の不満(例: 残業、給与)を解決すること!結局のところ会社のイメージ自体がブランドイメージに直結するのですね!
例: フレックスタイム導入、成果ボーナス設定。
社員のエンゲージメントを高める施策(例: 社内表彰、研修)を並行実施することも忘れずに。
継続的なコンテンツ発信:SNSやキャリアページで、定期的に社員の声や文化を発信することも重要です。
例: 月1回の「社員ストーリー」ブログ。
予算を広告だけでなく、長期的なコンテンツ(例: 動画、ブログ)に分散しましょう!
効果測定の多角化:応募数だけでなく、口コミスコア、エンゲージメント率、離職率を追跡し、ブランドイメージ向上における課題点を洗い出しましょう!
例: Google Analyticsでキャリアページの滞在時間を分析。
②ブランディングで魅力的なメッセージを発信していたが、採用プロセスで手間取ってしまい口コミサイトやSNSで 「応募したが1ヶ月連絡なし」と投稿が発生した。
【原因】
選考における「求職者が実際に体験したこと」も、そっくりそのままブランドイメージに直結します。
【改善策】
選考プロセスの標準化:当然ですが、応募から返信まで48時間以内、選考結果は1週間以内に通知することを心掛けましょう!それだけで求職者へのイメージ向上につながります。
例: 自動返信メールに「2日以内にご連絡します」と記載。
選考スケジュールと基準をキャリアページに公開しておくのも◎
例: 「1次ではスキルを、2次では企業とのマッチ度合いを中心に総合的に判断します」
フィードバックの徹底:不採用者に建設的なフィードバックを提供すると、イメージ向上に抜群の効果を発揮します。
例: 「スキルは高いが、今回は経験年数が不足のためお見送りといたします」。
採用者には、入社までのフォローアップ(例: 歓迎メール)を送り、離脱を防ぐことも重要です。
トレーニングとツール活用:面接官に「求職者とのコミュニケーション」トレーニングを実施しましょう。
例: 「企業の価値観を伝える方法」。
ATSツール(例: HRMOS、Taleo)で応募者管理を効率化するのもベストですね!
求職者アンケート:選考後に簡単なアンケート(例: 「選考プロセスはわかりやすかったですか?」)を実施し、改善点を特定すると、次回の改善に役立ちます!
理解できたでしょうか??選考における体験や、選考後のギャップをなくすことは、当然と言えば当然ですよね!しかし、その当然のことを継続して行うことが、採用ブランディング成功の近道なのです!
採用ブランディングで採用費用を下げる取り組み
採用ブランディングを行うことが採用を行ううえで強いことは理解できたかと存じますが、採用コストの下げ方はどうなのでしょうか!実は、採用ブランディングの一環で「いつの間にか下がっている」ケースが多いのです!主な「採用コストを下げるための施策」を紹介します!
①低コストの自社サイトやSNSを活用
採用HPの作成や、動画作成・SNSの活用等々、無料または低コストのチャネルで求職者を惹きつけ、求人広告の費用を削減が狙えます!
また、多数社員が発信することによって信頼性の高いコンテンツが増え、広告依存が減少する服地効果も狙えますね!
求人広告を掲載するには相応の金額が発生してしまいますが、「掲載費」を抑えられるだけでも十二分な価値がありますよ!
事例: 日本の小売企業がInstagramで「店舗スタッフの日常」を発信。社員5名がハッシュタグ「#店舗ライフ」で投稿し、広告費を50%削減。直接応募が40%増加。
②インバウンド採用を狙う
求職者が自ら応募するパイプラインを構築し、人材紹介会社やリクルーターのコストを削減することが可能です!
タレントプールやイベント開催、リファラル採用がこれにあたりますね!実際日本でもインバウンド採用により、人材紹介会社の手数料(1人当たり50-100万円)を削減した例もあります!
リファラル採用は、広告や紹介料より低コストなのもうれしいポイントですね(例: 紹介ボーナス1万円 vs. 紹介料50万円)。
事例: 日本の製造業が「地元学生向け工場見学」を開催。参加者から直接応募が増え、人材紹介会社への依存が40%減。採用コストが25%削減。
③口コミ点数増加による、広告費削減を狙う
ポジティブな口コミを増やし、求職者の信頼を獲得できると、広告やリクルーターへの依存を減らすことにつながります!
口コミの不満への解消への取り組みや、ネガティブな投稿への誠実な対応が求職者に対する「良いイメージ」につながるわけですね!ポジティブな口コミにより、求職者が自ら応募。広告費や紹介料が削減でき、40%のコストカット実現も狙えるとか…!
事例:小売企業がシフト改善と社員発信を実施。OpenWork評価が3.2から4.0に向上、広告費が40%削減。
採用ブランディングの基本とは?成功するための戦略と実践方法解説
まとめ
採用ブランディングの基本についてご紹介しました。
実際、各部署への社内調査やEVPの設定を行っている企業は少ないです。「そこまで手が回らない」「忙しくて時間がない」といった理由から、このプロセスを省略してしまうケースも少なくなのが現実です。
しかし、このプロセスを疎かにすると、結果的に採用のやり直しや早期離職につながってしまい、かえって大きな手間とコストがかかってしまいます。だからこそ、最初の計画と調査の段階に時間をかけることが、長い目で見ても最も効率的な採用活動になります。
また、採用ブランディングは計画通りに進まないこともありますが、適切な対応を講じることで十分に挽回可能です。
求人広告代理店である株式会社bサーチは、中途採用の広告支援(dodaやマイナビ、リクナビNEXT)の取り扱いだけでなく、採用ブランディングにおける課題解決もサポートします。
これまでの実績、ノウハウを駆使し採用のお手伝いをさせていただきます。
採用活動に関してお困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。採用ブランディングならBE GOOD

