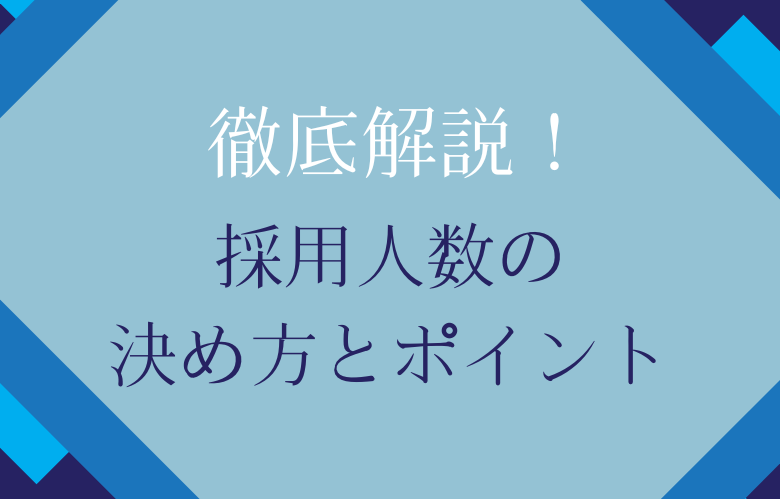
「採用人数の決め方が分からない…」このようなお悩みはありませんか?
事業拡大や新卒募集などのタイミングで、何人に設定すればよいか悩んでいる人事担当者の方は多いと思います。
採用人数の目安は企業の規模によって異なります。例えば、新卒採用の割合の平均値は、企業規模が500人未満の場合、5.1%と言われています。つまり、企業規模100名当あたり3~5名が目安となります。しかし、この数値はあくまで平均値となります。より適正な採用人数を決定するには、今後の事業計画なども踏まえて慎重に検討する必要があります。
そこで本記事では、採用人数の決め方やポイントを丁寧に徹底解説します。さらに、記事の後半では設定した人数に達しなかった場合の対処法も分かりやすくまとめました。
ぜひ本記事を参考に、採用成功に繋げてください。
目次
【採用人数の決め方①】自社の事業計画を確認する
まず始めに行うことは、自社の事業計画の確認です。事業計画には、会社の中長期的なビジョンや数値目標、組織体制、新規事業の立ち上げなどの会社の成長戦略が具体的に記載されています。これらの内容を正確に把握することで、より適正な採用人数を感覚ではなく、ロジカルかつ戦略的に決めることができます。
例えば、下記のような事業内容があったとします。
◎3年以内に内製化を進める予定
➡業務の外注コストを削減し、社内でノウハウの蓄積をする必要があるため、3年以内に専門スキル(例:マーケティング・システム開発・デザイン系など)を持った人材を継続的に採用、育成していく必要があります。また、組織や業務フローの混乱を防ぐため、1度にまとめて採用するのではなく、計画的に段階を踏んで採用していくことが良いでしょう。
◎来年に新しいプロジェクトを立ち上げる予定
➡新規プロジェクトのための準備期間を考慮すると、プロジェクト開始の“半年前まで”には採用が完了していることが理想です。事業計画に基づいて、採用する時期も逆算することが大切です。
◎来年は今年よりも顧客数の増加を見込んでいる
➡顧客対応力の強化が必要になるため、今のうちからカスタマーサポートや営業部門の人員を強化する必要があります。また、現状の社員だけで、どれくらいの業務量を対応できるか数値を見積もったうえで採用すべき人数を決められると尚よいです。
このように、人材ニーズは事業計画の内容次第で大きく変化します。自社の計画内容を改めて確認し、「いつ・どの部署に・どのような人材を・何人必要とするか」を具体的に洗い出すことが採用の第一歩となります。単に、人が足りないから採用するのではなく、採用人数の根拠を明確にすることで、人材の定着にも繋がりやすくなります。
【採用人数の決め方②】意外と実践している企業は少ない!各部署への人材ニーズの調査
適正な採用人数を洗い出すうえで欠かせないステップが、「各部署における人材ニーズの調査」です。ここでは採用人数の把握だけでなく、「どのような人材が」「どれだけ必要か」を明確にしていきます。採用計画全体の制度を高める上でとても重要な作業になります。
各部署の業務実態や、組織の課題を把握せずに採用活動を進めてしまうと、入社後にミスマッチが起こりやすく、せっかく採用した人材が早期離職してしまうリスクも高まります。各部署ごとの人材ニーズを把握することで、採用活動の“土台”を正しく構築することができます。
なぜ人数を決めるにあたって人材ニーズの調査が重要なのか
多くの企業で見られるのが、「なんとなく人が足りなさそう」「前年と同じ採用数にしておこう」といった曖昧な基準での採用人数の設定です。これでは、組織課題の根本的な解決につながらず、結果として無駄なコストやミスマッチを生んでしまうこともあります。具体的に、人材ニーズを明確にすることで以下のようなメリットが生まれます。
■採用ミスマッチの防止
各現場の「求めるスキルや人物像」が明確になることで、選考時の判断基準がクリアになります。このことにより、「仕事内容が思っていたよりも自分に合わなかった」などといった、採用ミスマッチのリスクが減少します。
■採用コストの最適化
本当に必要な人材だけを的確に採用できるようになるため、無駄なコストを省くことができます。
■採用活動の効率化
部署ごとのニーズを整理することで、採用活動においての優先順位やスケジュールなどを立てやすくなります。
■優秀な人材の獲得につながる
求める人材が明確になれば、人事部内での選考基準がぶれないため、優秀な人材の獲得につながります。
ヒアリング調査の具体的な進め方
人材ニーズの調査では、各部署の責任者(マネージャー、リーダーなど)へヒアリングを行い、現場の状況や将来的な人員計画を把握していきます。
「人手が足りているか」ではなく、「どのようなスキルを持った人材が必要か」「なぜその人材が必要なのか」というように、深堀りをして情報収集することがポイントです。
【ヒアリング調査の質問項目】
・現在のチーム人数で、仕事量に無理はないですか?
→残業時間やメンバーの業務負荷の偏りも確認します
・今後1年間で新しいプロジェクトや業務の拡大予定はありますか?
→短期的ではなく、中長期的な視点でも確認します
・退職・休職・異動などにより欠員が生じる予定はありますか?
→フォロー体制や引き継ぎの有無も確認できると尚よいです
・現在のチームに不足しているスキルや経験はありますか?
→現場の困りごとを、人材でどのように補う必要があるかが見えてきます
・理想的な人材像(スキル面・人物面)はどのようなものですか?
→技術力だけでなく、性格や志向なども掘り下げていきます。
・過去に採用した人材で、成果を上げた人・うまくいかなかった人の特徴は何ですか?
→採用成功・失敗の要因分析として有効です
調査結果の可視化と共有
ヒアリング後は、収集した情報を各部署ごとに「採用ニーズ一覧表」などのフォーマットにまとめると、全体の状況が一目で把握しやすくなります。
例えば、以下のような情報を一覧表に整理しておくと、採用計画を戦略的に立てることができます。
〈採用ニーズ一覧表〉
■配属予定部署
■職種
■採用予定人数
■採用理由・背景
■求めるスキル・経験
■求める人物像
■採用時期
■優先度(高・中・低)
■備考・補足
また、採用ニーズ一覧表の具体的な記載例も下記にまとめました。
〈採用ニーズ一覧表記載例①〉
■配属予定部署:営業部
■職種:法人営業
■採用予定人数:2人
■採用理由・背景:新規案件増加による対応強化
■求めるスキル・経験:BtoB営業経験をお持ちの方(業界・年数不問)
■求める人物像:積極性・論理的思考
■採用時期:2025年10月
■優先度(高・中・低):高
■備考・補足:同業界であれば尚可
〈採用ニーズ一覧表記載例②〉
■配属予定部署:開発部
■職種:エンジニア
■採用予定人数:1人
■採用理由・背景:新規プロジェクト立ち上げのため
■求めるスキル・経験:JavaScript、Reactの開発経験
■求める人物像:協調性や積極性がある方
■採用時期:2026年1月
■優先度(高・中・低):中
■備考・補足:即戦力として活躍できる方がいい
ヒアリング調査にて、部署ごとのニーズを“見える化”することで、採用人数の決定はもちろん、経営層や人事内での共有もスムーズに行え、組織全体として一貫性のある採用活動を進めやすくなります。また、採用ニーズ一覧表を共有する際に、各項目ごとに理由や背景を記載しておくと、より納得感が高まります。
このように、単に「人が足りているか」ではなく、「なぜ必要なのか」「どのような人材が必要か」といった具体的な視点からニーズを掘り下げていくことで、採用の質と効率も高めることができます。
【採用人数の決め方③】適正な数値を決定する
1章と2章で得た事業計画と各部署の人材ニーズを元に、最終的な採用人数を決定していきます。ここで有効となるのが、「トップダウン方式」と「ボトムアップ方式」の2つです。両者を組み合わせることで、全体的なニーズと現場のニーズのバランスが取れた、人材を決定することができます。
トップダウン方式:事業計画の内容を反映させる
トップダウン方式とは、企業の事業計画に基づいて採用人数を算出する手法です。例えば、第1章で述べたように、「3年以内に内製化を進める予定」「来年に新しいプロジェクトを立ち上げる予定」「来年は今年よりも顧客数の増加を見込んでいる」などの指標をもとに、会社全体で必要とされている人員を逆算していきます。
この方法では、経営層が「会社全体でどれだけの人材が必要か」を把握できるため、予算管理や長期的な組織戦略との整合性を確保しやすい点がメリットです。
ボトムアップ方式:現場のニーズを反映させる
一方、ボトムアップ方式は、各部署にヒアリング調査した内容をもとに必要な人数を算出していく方法です。
退職予定者の有無や新規プロジェクトの開始予定など、現場で実際に起こっていることをベースに必要人員を決めていきます。
ボトムアップ方式を用いることにより、現場の声を採用計画に取り込むことができます。結果、業務負荷や人員不足のボトルネックを解消することができます。
基本的な流れとしては、まずトップダウン方式を用いて採用人数の大枠を決め、その後、ボトムアップ方式を用いて各部署の要望を照らし合わせながら具体的な採用人数を調整していきます。両社の数値にギャップが生じた場合は、事業への貢献度や業務の代替の可能性など優先順位や緊急度を考慮して、採用計画全体の見直しや再調整を行います。
新卒・中途関係なく適用できる!具体的な算出方法の例
それでは、採用人数の算出方法を具体的な例を挙げて解説します。
事業計画が、「半年後に月間売上700万円達成」であったとします。売上達成のために、お客様と商談する営業の採用人数を算出していきます。
まずは事業計画より、必要な活動量を算出します。
例えば、1件成約すると約10万円の売り上げになるとすると、月70件(700万円÷10万円)の成約が必要になります。さらに、平均成約率が10件中1件であった場合、必要な商談件数は700件(70件×10%)となります。
次に、現状の社員でどこまで対応が可能かを把握します。現在の社員数で500商談しているとすると、必要な商談件数は200商談(700商談ー500商談)となります。
最後に、社員1人の行動量を計算します。現在の社員で1日5商談しているとすると、20営業日で100商談(5件×20営業日)。同じ即戦力の社員を採用する場合、残り200商談を行うためには、社員を2人(200件÷100件)を増員する必要があると判断することができます。
最終決定において、「事業計画に沿った根拠ある人数になっているか」「ヒアリング調査にて露になった採用ニーズが適切に反映できているか」の2点を押さえることで、戦略と現場の両方にとって納得感のある採用人数を導き出すことができます。
採用が難しい…まだ諦めないでください。目標予定人数に達しなかった場合の対処法3選
採用活動を進めていく中で、設定した目標人数に到達しないことは決して珍しくありません。競合企業との採用競争の激化や、応募者側の志向の変化などといった外部的な要因も多く影響します。
しかし、そこで諦めずにリカバリーしていくことで、採用成功のカギとなります。万が一、設定した目標採用人数に到達しなかった場合は、以下のご紹介する3つの方法を活用し、採用成功を目指しましょう。
選考に進まなかった候補者への再アプローチ
まず検討すべきは、エントリーはしたものの、選考に進まなかった候補者へのアプローチです。会社説明会などのイベントに参加していたということは、少なからず企業に対して興味を持っていたからです。
選考に進まなかった理由には、「他社の日程とかぶってしまった」「急用で行けなくなってしまった」など、やむを得ないケースも考えられます。したがって、このような候補者へは、今一度アプローチする価値が十分にあります。
この場合は、単なる説明会の案内ではなく「★特別オファー★面接のご案内★」といったように、選考直結型のオファー形式での招待を行うことが効果的です。加えて、面談にて「なぜ選考に進まなかったのか」「現在の就活状況はどうか」などを丁寧にヒアリングすることで、候補者理解が進み、的確なクロージングにもつながります。
選考辞退者にアプローチする
続いては、一度選考に進んだものの、途中で辞退した候補者への再アプローチです。辞退理由には、「他社と迷った」「日程などのタイミングが合わなかった」「就活を一時中断した」など、ポジティブな動機での辞退も少なくありません。
このような候補者は、選考を経験しているため、企業に対する理解も深く、再アプローチが実を結ぶ可能性が高いです。
アプローチする際は、電話やメールだけでなく、状況に応じて個別面談やオンライン面談の提案も有効です。単に再応募を促すだけではなく、「前回ご辞退された際の背景をお聞かせいただきたく…」と相手の立場へ寄り添う丁寧なコミュニケーションを意識しましょう。特に応募者の就職活動状況が変化している時期であれば、再チャレンジの可能性も十分にあります。
採用プロセスの再構築を行う
候補者と辞退者の双方に再アプローチをしても成果が出ない場合は、採用活動自体を見直す必要があります。まずは、母集団形成方法などを振り返り、どこに課題があったか分析しましょう。「どの媒体からの応募が少なかったか」「選考辞退が集中したフェーズはどこか」などデータをもとに改善策を練る必要があります。
また、新たなアプローチとして、下記のような施策もおすすめです。
・採用媒体や求人広告の再掲載(ターゲット層を変える)
・SNS採用(instagramやXなどでの起業発信を強化する)
・リファラル採用(社員紹介制度の活用)
・ダイレクトリクルーティング(スカウト型のサービスの導入)
このように、プロセス全体を見直すことで、従来の手法では出会えなかった優秀な人材との接点が生まれ、採用成功率の向上が期待できます。
まとめ
この記事では、採用人数の決め方についてご紹介しました。
ニーズ調査などは、自社の採用ニーズに合わせてアレンジを加えてみるのもいいでしょう。
実際、自社の事業計画の確認や各部署への人材ニーズ調査を行っている企業は少ないです。「そこまで手が回らない」「忙しくて時間がない」といった理由から、このプロセスを省略してしまうケースも少なくなのが現実です。
しかし、このプロセスを疎かにすると、結果的に採用のやり直しや早期離職につながってしまい、かえって大きな手間とコストがかかってしまいます。だからこそ、最初の計画と調査の段階に時間をかけることが、長い目で見ても最も効率的な採用活動になります。
また、採用活動は計画通りに進まないこともありますが、適切な対応を講じることで十分に挽回可能です。採用戦略の見直しや候補者への再アプローチを柔軟に行い、最適な人材の獲得につなげていきましょう。
求人広告代理店である株式会社bサーチは、中途採用の広告支援(dodaやマイナビ、リクナビNEXT)の取り扱いだけでなく、面接時における課題解決もサポートします。
これまでの実績、ノウハウを駆使し採用のお手伝いをさせていただきます。
採用活動に関してお困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

