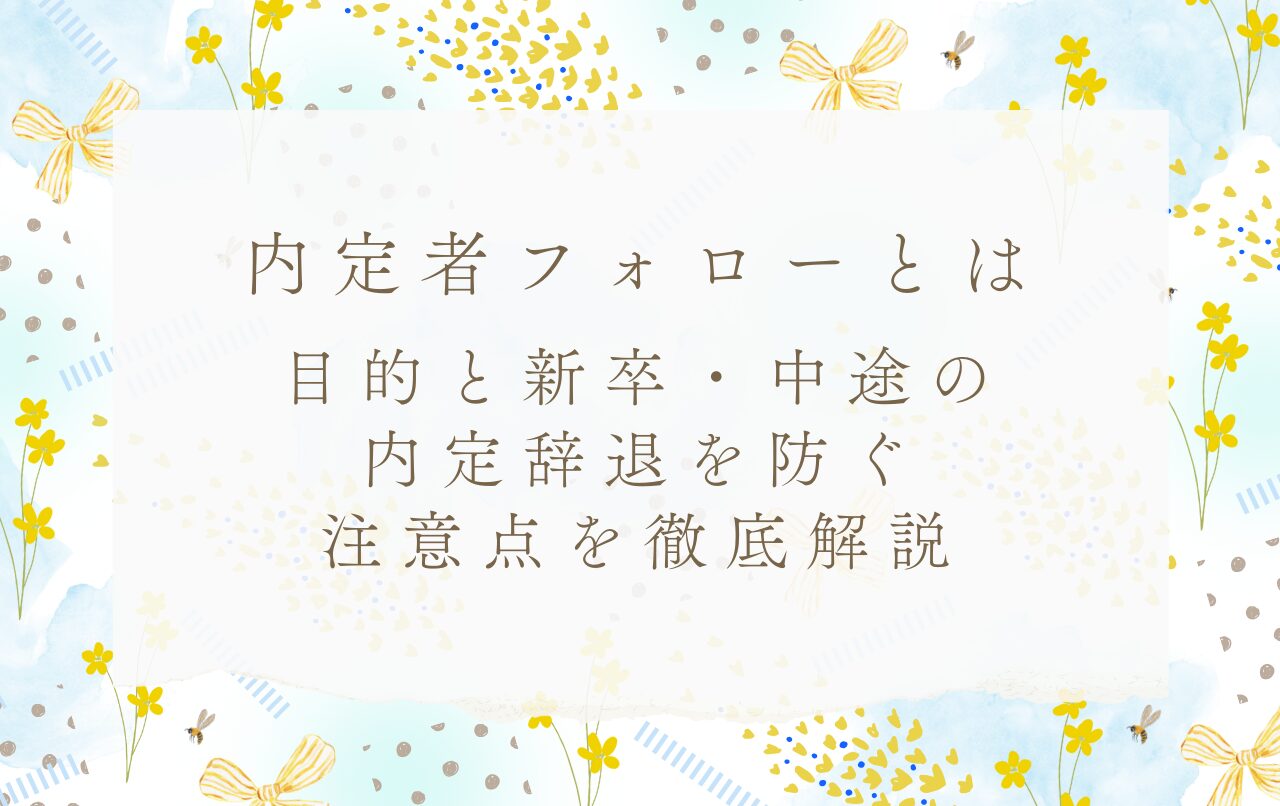
内定者フォローとは、企業が内定者に対して入社までの期間に提供する、さまざまなサポート施策のことを指します。
内定者フォローを行うことにより内定者の入社に対する不安を解消し、モチベーションを高め、企業への理解を深めてもらうことができます。
具体的には、内定者懇親会や人事担当者からの定期的な連絡、職業体験の機会提供、内定者同士の早期コミュニティ形成支援など多岐にわたります。
目次
内定者フォローの目的は内定辞退の防止と入社後の早期離職の防止
内定者フォローの目的は、大きく分けて「内定辞退の防止」と「入社後の早期離職の防止」の2つが挙げられます。
まず、内定辞退の防止とは、せっかく内定を出した優秀な人材が他社に流れることを防ぐことです。
近年は「超売り手市場」と呼ばれ、学生は複数の企業から内定をもらうことが珍しくありません。
企業は、内定者に自社の魅力を再確認してもらい、入社への期待感を高めるための対策が必要です。
具体的な施策としては、内定者懇親会や社員との交流会を通じて、社内の雰囲気や人間関係を事前に知ってもらい、学生が抱く不安を解消することが挙げられます。
これにより、入社へのモチベーションを維持し、内定辞退のリスクを低減させることができます。
次に、入社後の早期離職の防止とは、入社した社員が短期間で退職してしまうことを防ぐことです。
新卒社員は、入社後の仕事内容や人間関係に対して不安を抱いていることが多く、「この仕事に向いているのか」「職場の人間関係はうまくいくのか」といった漠然とした不安を解消することが、内定者フォローの重要な目的となります。
例えば、内定者研修や先輩社員との面談を通じて、仕事の具体的なイメージを掴んでもらったり、入社前に内定者同士のコミュニティを形成したりすることで、入社後のギャップを減らし、早期離職を防ぐ効果が期待できます。
内定者フォローは、内定者の不安を期待と自信に変え、企業への信頼感を高めることで、定着率向上にも繋がる重要な取り組みと言えるでしょう。
内定者フォロー施策を行う時のポイント4選
内定者フォローは、単に内定辞退を防ぐだけでなく、入社後のミスマッチを解消し、早期離職を防ぐためにも欠かせない取り組みです。
こちらの章では、内定者フォローを行う際のポイントを4点ご紹介します。
具体的には下記のとおりです。
・企業への理解度と志望度を高める
・内定者の印象に残る内定通知をおこなう
・社員とコミュニケーションをとる機会を設ける
・定期的に連絡をとる
詳しくご紹介していきます。
【内定者フォロー施策①】企業への理解度と志望度を高める
内定者フォロー施策の1つ目は、内定者の企業理解度と志望度を高めることです。
学生は選考過程で複数の企業を受けていることが多く、内定を得たとしても、必ずしも志望度が高いとは限りません。
そのため、企業側は内定者に自社の魅力を再認識してもらい、入社への期待感を高めるためのフォローが不可欠です。
具体的には、内定者が抱く「本当にこの会社に入社して良いのか」「実はこの会社についてよく知らないのではないか」といった不安を解消し、期待と自信に変えることが重要です。
内定者は入社後の自身の姿を具体的にイメージしやすくなり、「この会社で働きたい」「この会社ならやっていけそうだ」という期待感を抱きやすくなります。
内定者が企業への理解を深め、自社で働くことへの魅力を感じられるようにサポートすることで、内定辞退の防止に繋がります。
【内定者フォロー施策②】内定者の印象に残る内定通知をおこなう
内定者フォロー施策の2つ目は、内定通知の伝え方です。
内定通知は、選考を通過した方に対して、企業が正式に入社を打診する大切な連絡です。
この内定通知の伝え方一つで、相手に与える印象は大きく変わります。
複数の企業から内定を獲得している可能性もあるため、記憶に残るインパクトのある通知が他社との差別化に繋がります。
たとえば、プロ野球のドラフト会議で指名された選手が、当初は他球団を希望していたにもかかわらず、監督が直接連絡をくれたことで入団を決意する事例は有名です。
これは、単なる書面やメールでの通知ではなく、「誠意」あるアプローチが学生の心を動かす好例と言えるでしょう。
一般の採用においても、同様の戦略が有効です。
例えば、社長や役員が直接電話で連絡したり、わざわざ出向いて内定を伝えたりするなど、他の企業ではなかなか見られない特別な対応は、「この会社は自分を本当に必要としてくれている」という強い印象を与え、入社への意欲を高めるきっかけとなります。
特に、現在の採用市場は売り手市場であり、求職者優位の状況です。
そのため、企業側は単に「内定を出した」で終わらせるのではなく、一人ひとりに寄り添い、特別な体験を提供することが、内定辞退防止の鍵を握るのです。
インパクトのある内定通知は、単なる事務的な連絡を超え、企業と求職者の最初の「心の繋がり」を築く重要な機会となるでしょう。
【内定者フォロー施策③】社員とコミュニケーションをとる機会を設ける
内定者フォロー施策の3つ目は、自社の社員とコミュニケーションを取る機会を設けることです。
内定者は入社前に「職場の雰囲気に馴染めるか」「業務をきちんとこなせるか」といった様々な不安を抱えているため、社員との交流を通じてこれらの不安を解消し、入社への期待感を高めることができます。
先輩社員との交流によって、職場のリアルな話を聞けたり、仕事のやりがいを感じられたりすることが、内定者の企業理解を深めるきっかけとなるでしょう。
これにより、入社後の人間関係への不安が軽減され、企業への帰属意識も高まる効果が期待できます。
社員とのコミュニケーションは、内定者が「この会社で働きたい」「この会社ならやっていけそうだ」と感じるための重要な要素です。
メンタリング制度を導入し、先輩社員が内定者の疑問や不安に寄り添ってアドバイスを行う体制を整えることも、内定者の安心感に繋がります。
【内定者フォロー施策④】定期的に連絡をとる
内定者フォロー施策として、定期的な連絡は内定者とのつながりを維持し、入社までの期間の不安を解消するために非常に重要です。2024年卒の就活生を対象とした調査では、内定承諾企業との連絡頻度について、半数以上(53.5%)が「月1回程度連絡を取りたい」と回答しています。文系・理系ともに同様の傾向が見られ、内定者が企業からの連絡を一定の頻度で望んでいることがうかがえます。
具体的な連絡内容としては、入社までのスケジュール共有や入社準備に必要な情報提供が挙げられます。例えば、内定者に課題を出し、提出された成果物に人事担当者や現場社員がコメントを記載してフィードバックするのも有効な方法です。 細かい部分までアドバイスすることで、内定者は企業に対して信頼感を持ちやすくなります。また、不明点や要望を確認し、必要に応じてサポートを実施することで、内定者は安心して入社準備を進められるでしょう。
特に、内定から入社までの期間が長い場合、定期的な連絡が途絶えると、内定者は「本当に歓迎されているのか」といった不安を抱きやすくなります。 連絡が遅れると不信感を抱く可能性もあるため、質問への返信は迅速に行うことが大切です。 適切な連絡頻度と丁寧なコミュニケーションは、内定者の入社意欲やモチベーションの向上に繋がり、内定辞退の防止にも効果を発揮します。
内定者フォローの事例|辞退を防ぐためのコツを解説
内定者フォローは、企業が内定辞退を防ぐための重要な施策です。
新卒採用と中途採用でそれぞれ効果的な事例があります。
■新卒採用
・学生との面談
・内定者懇親会
・内定式での工夫
・内定者研修
・合宿研修
■中途採用(新卒採用でも実施可)
・座談会
・職場見学
・社内イベント
・社内報の送付
内定者の不安を解消し、入社意欲を高めることで、辞退防止に繋がります。
こちらの章では上記に挙げた事例を詳しくご紹介していきます。
新卒採用の場合
新卒採用の場合における内定者フォローは、学生が抱える入社への不安を解消し、企業への理解を深めてもらうことを目的とします。
学生が安心して入社を迎えられるよう、懇親会や面談、研修などを通して、きめ細やかなサポートを実施することが重要です。
【新卒採用|事例①】学生との面談を実施する
新卒採用1つ目の事例は学生との面談です。
面談を実施し、内定者一人ひとりと個別、または少人数で話す機会を設けます。
この面談を通じて、学生が抱える入社前の疑問や不安を直接聞き出し、個別に丁寧なフォローを行うことが可能です。
人数でのコミュニケーションが苦手な学生や、個人的な悩みを抱えている学生にとっては、面談が本音で話せる貴重な場となります。
面談の頻度や時期は、内定者の状況や企業の方針によって調整することが重要です。
一般的には、内定通知後から入社までの期間に複数回実施することが望ましいとされています。
特に、内定を出した直後や、入社直前の時期は学生の不安が高まりやすいため、重点的に面談の機会を設けることが効果的です。
例えば、内定通知から1ヶ月後、その後は2〜3ヶ月に一度の頻度で定期的に面談を設定し、入社直前には再度個別面談を行うことで、学生は安心して入社日を迎えられます。
面談を通じて、企業は内定者の性格や価値観を深く理解し、入社後の配属や育成に役立てることも可能です。
【新卒採用|事例②】内定者懇談会を実施する
新卒採用2つ目の事例は内定者懇談の実施です。
内定者同士が交流を深める重要な機会であり、入社前の不安を解消し、企業への帰属意識を高める効果があります。
特に、就職活動を通して同期との関係構築に不安を感じている学生にとって、懇談会は良好な人間関係を築くための第一歩となるでしょう。
最近では、場所や時間に縛られずに参加できるオンライン形式での開催も増えており、遠方に住む内定者や学業などで多忙な内定者も参加しやすいというメリットがあります。
懇談会の内容としては、内定者同士の自己紹介やグループディスカッションを通じて、お互いの共通点や興味関心を探るプログラムが効果的です。
例えば、簡単なゲームやチームビルディング研修を取り入れることで、自然な形でコミュニケーションを促進できます。
また、懇談会の後半には食事会を設け、リラックスした雰囲気の中で会話を楽しんでもらうのも良いでしょう。
食事を共にすることで、より打ち解けた雰囲気になり、普段話せないようなプライベートな話題に触れるきっかけにもなります。
さらに、懇談会では、企業側から事業内容や職場の雰囲気、今後の研修計画などを具体的に説明する時間も設けることで、内定者の企業理解を深めることができます。
これにより、入社後のミスマッチを防ぎ、入社へのモチベーションを向上させる効果が期待できます。
特に、具体的な研修内容や入社後のキャリアパスを示すことで、内定者は自身の成長イメージを描きやすくなります。
【新卒採用|事例③】内定式を工夫する
新卒採用3つ目の事例は内定式を工夫することです。
内定式は内々定を出した学生に正式な内定を通知する大切な機会です。
この内定式を工夫することで、学生に強い印象を与え、他社との差別化を図ることができます。
単に内定を通知するだけでなく、内定式の「目的」を再確認し、内定者フォローに繋がる「企画」を検討することが重要です。
例えば、採用担当者ではなく、社長や役員が直接内定通知書を手渡すことで、企業からの歓迎と期待を強く伝えることができます。
また、役員との対談機会を設けることで、企業のビジョンや経営者の考えに触れることができ、学生は企業への理解を深めると同時に、入社への意欲を高めることができるでしょう。
これは、単なる通知ではなく、学生に「内定した」という実感を強く持たせる効果があります。
近年では、新型コロナウイルスの影響もあり、対面での内定式が難しいケースが増えています。
そのため、「オンライン」形式での内定式を実施する企業も多く見受けられます。
オンラインでも工夫次第で、学生の心に残る内定式は開催可能です。
例えば、内定者同士の交流を促すグループワークを取り入れたり、企業の「ライン」でのメッセージ機能を活用して、役員や先輩社員からのメッセージを届けるといった方法も有効です。
オンラインだからこそできる企画を検討し、内定者との心理的な距離を縮めることが大切です。
【新卒採用|事例④】内定者研修をおこなう
新卒採用4つ目の事例は内定者研修です。
内定者研修は内定者が社会人として必要な基礎知識や心構えを習得する大切な機会です。
例えば、ビジネスマナーや報連相の基本、OAスキルなど、入社後に役立つ具体的な内容を盛り込むことで、内定者はスムーズに業務に移行できます。
内定者を集めて行う研修は、同期との連帯感を醸成し、チームワークを育むきっかけにもなります。
特に、グループワークやディスカッションを取り入れることで、お互いの個性や強みを理解し、協力して課題に取り組む経験を積むことが可能です。
ただし、研修の内容が難しすぎると、内定者のモチベーション低下に繋がりかねません。
そのため、内定者が楽しみながら学ぶことができるよう、簡単なテーマからスタートし、徐々に専門的な内容へと進めるのがおすすめです。
例えば、企業の歴史や理念を学ぶワークショップ、先輩社員との交流を通じた座談会形式の研修など、内定者が主体的に参加できるような工夫が重要です。
これにより、入社への期待感を高め、入社後の早期離職防止にも繋がります。
また、研修の実施方法として、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド形式も有効です。
遠方に住む内定者や学業との両立で多忙な内定者でも参加しやすくなり、多様な内定者に配慮した研修を提供できます。
研修の最後には、内定者からのフィードバックを募り、次回の研修内容に活かすことで、より効果的な研修プログラムへと改善していくことができるでしょう。
【新卒採用|事例④】合宿研修をおこなう
新卒採用5つ目の事例は合宿研修です。
合宿研修は、数日間かけて集中的に実施する研修方法です。
宿泊を伴うため、内定者同士はもちろん、社員とも深い交流の機会が生まれ、仲間意識を効果的に強化できます。
この研修では、企業理念や事業内容の理解を深めるためのプログラムや、社会人としての基礎となるビジネスマナーの習得、プロジェクト型学習による問題解決能力の向上など、多岐にわたる研修内容を盛り込むことが可能です。
特に、内定者が一体となって課題に取り組むチームビルディング形式の活動は、入社後のスムーズな連携に繋がる貴重な経験となります。
しかし、合宿研修の実施には、まとまった予算と人手の確保が不可欠です。
施設利用料や講師費用、宿泊費、食費など、コストが膨らむ傾向にあるため、費用対効果を慎重に検討し、得られるメリットを最大化するための計画が求められます。
また、内定者にとって肉体的・精神的な負担が過度にならないよう、研修スケジュールや内容に配慮することも重要です。
例えば、研修の合間に休憩時間を十分に設けたり、個人の意見を尊重するようなグループワークを取り入れたりすることで、内定者が前向きに取り組める環境を整えることができます。
合宿研修は、内定者のエンゲージメントを高め、入社後の活躍に繋がる重要な投資となるでしょう。
中途採用の場合(新卒採用でも導入可)
中途採用者に対する内定者フォローは、新卒採用と同様に入社前の不安を解消し、企業への理解を深めてもらうことを目的としています。
中途採用者はこれまでの職務経験があるため、即戦力としての期待が大きい一方で、新しい職場環境や企業文化への適応に対する不安を抱えている場合も少なくありません。
そのため、新卒採用の施策と共通する部分も多いですが、中途採用者の経験やスキル、キャリアプランに合わせた個別のフォローが重要となります。
ここからは、中途採用者にも有効な内定者フォローの具体的な施策についてご紹介していきます。
新卒採用でも導入可能な内容ですので、ぜひご覧ください。
【中途採用|事例①】座談会の実施
中途採用1つ目の事例は座談会の実施です。
中途採用者向けの座談会は、内定者と既存社員が交流する機会を提供することで、入社への不安を解消し、企業への理解を深めてもらうことを目的としています。
座談会で現場の若手社員やベテラン社員、管理職など多様な層の社員と交流することで、内定者は実際に働く自身の姿を具体的にイメージしやすくなります。
この座談会を成功させるためには、参加する社員の選定と、座談会の目的を明確に伝えることが重要です。
参加社員が内定者に対して誠実で、会社の魅力を伝えられるような人物であるかを見極める必要があります。
例えば、中途入社経験のある社員をアサインすることで、内定者の共感を呼び、より具体的なアドバイスを提供できるでしょう。
また、社員には座談会が単なる交流会ではなく、内定者の入社意欲を高め、企業へのエンゲージメントを築くための重要なステップであることを理解してもらうことが大切です。
これにより、社員は内定者の疑問や不安に対して適切に対応し、会社の良い雰囲気を伝えることができるようになります。
【中途採用|事例②】職場見学の開催
中途採用2つ目の事例は、職場見学の開催です。
中途採用における職場見学とは、内定者が実際に入社する前に職場の雰囲気や働く環境を直接確認できる貴重な機会です。
その主な目的は、入社後のミスマッチを防ぎ、内定者の入社意欲を高めることにあります。
具体的には、選考の最終確認として行われることが多く、内定承諾の前に「自身のイメージと食い違っていないか」を確認したり、入社を前提として「準備すべきこと」を把握したりする目的があります。
職場見学を通じて、内定者は実際に働く社員の様子やデスクの配置、使用しているツール、備品などを肌で感じることが可能です。
これにより、入社後の具体的な働くイメージが湧きやすくなり、漠然とした不安の解消に繋がります。
しかし、職場見学には課題もあります。
企業によっては機密情報の漏洩リスクやセキュリティ上の問題から、外部の人間を社内に入れることが難しい場合があります。
また、見学の実施には人事担当者だけでなく現場社員の協力も不可欠であり、事前の準備や調整に時間と手間がかかることも課題の一つです。
近年では、こうした課題に対応するため、オンラインでの職場見学も増えています。
オンライン形式であれば、遠方に住む内定者や現職が忙しい内定者でも場所や時間にとらわれずに参加しやすくなります。
また、事前に会社のオフィスや一緒に働くメンバーの写真や動画を用意しておくことで、職場の雰囲気を伝えやすくなります。
さらに、ラインなどのメッセージツールを活用して、オンライン見学後の質疑応答を行うことも、内定者の疑問解消に効果的です。
【中途採用|事例③】社内イベントへの参加
中途採用3つ目の事例は、社内イベントへの参加を促すことです。
内定者が企業文化や職場の雰囲気を肌で感じ、入社への不安を解消するために非常に効果的です。
特に中途採用の場合、即戦力としての期待が大きい反面、新しい環境への適応に不安を感じることも少なくありません。
社内イベントは、開放的な雰囲気の中で既存社員とコミュニケーションを図る絶好の機会となり、内定者の入社に対するモチベーション向上に繋がります。
近年、新型コロナウイルス感染症の影響により、大人数が集まるイベントの開催が難しい状況が続いていますが、オンラインでのイベント開催は有効な選択肢です。
オンラインイベントであれば、地理的な制約やコロナ禍での移動制限を気にすることなく、多くの内定者が気軽に参加できます。
例えば、オンラインでの歓迎会や交流会、部門ごとのカジュアルな座談会などを企画することで、内定者は自宅から会社の雰囲気を知ることが可能です。
実際に、中途入社者向けのオンライン歓迎会を実施している企業もあり、同期入社者や既存社員との交流を深める場として活用されています。
ただし、参加を強制するのではなく、あくまで自主的な参加を促すことが重要です。内定者が自身のペースでイベントに参加できるよう配慮することで、安心して入社を迎えられる環境を整えられます。
【中途採用|事例④】社内報の送付
中途採用4つ目の事例は、内定者へ社内報送付です。
社内報とは、企業が社員向けに発行する情報誌のことで、会社の理念や事業内容、社員紹介、社内イベントの様子などが掲載されています。
内定者が社内報を手にすることで、企業の文化や雰囲気をより具体的に理解し、入社後のイメージを膨らませやすくなるでしょう。
しかし、単に資料を送るだけでは、効果的な内定者フォローとは言えません。
送付する社内報が、内定者が自社に対する理解を深められる内容であるか、また、入社への期待感を高められるものであるかを吟味する必要があります。
例えば中途採用者であれば、過去の中途入社者のインタビュー記事や、部署ごとの業務内容が詳しく紹介されているページをピックアップして送付するなど、内定者の関心に合わせた工夫が有効です。
加えて、社内報の送付と合わせて、人事担当者や現場社員からのメッセージを添えることも重要です。
例えば、「この社内報を通じて、弊社の働き方や雰囲気を少しでも感じていただけたら幸いです。もし気になる記事や質問があれば、いつでもご連絡ください」といったメッセージを添えることで、内定者は企業からの歓迎をより強く感じ、疑問点を気軽に尋ねやすくなります。
このような細やかな配慮が、内定者のエンゲージメントを高め、入社意欲の向上に繋がるのです。
まとめ
内定者フォローは、企業が優秀な人材を確保し、入社後の活躍を支援するために不可欠な取り組みです。
本記事では、内定者フォローの説明と目的、辞退を防ぐための方法についてご紹介をさせていただきました。
内定者フォローは単なる事務的な対応ではなく、内定者の未来を支援し、企業の成長に貢献する重要な戦略です。
特に、内定辞退の防止や入社後の早期離職防止という明確な目的を達成するために、個々の内定者に合わせた細やかなサービスを提供することが求められます。
株式会社bサーチでは、お客様の状況に応じた内定者フォローの研修や施策の導入支援を行っております。
採用戦略の立案から、採用動画や資料制作、LP作成などの具体的な施策まで幅広く対応しており、貴社の採用活動を強力にサポートいたします。
内定者フォローの充実にご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

